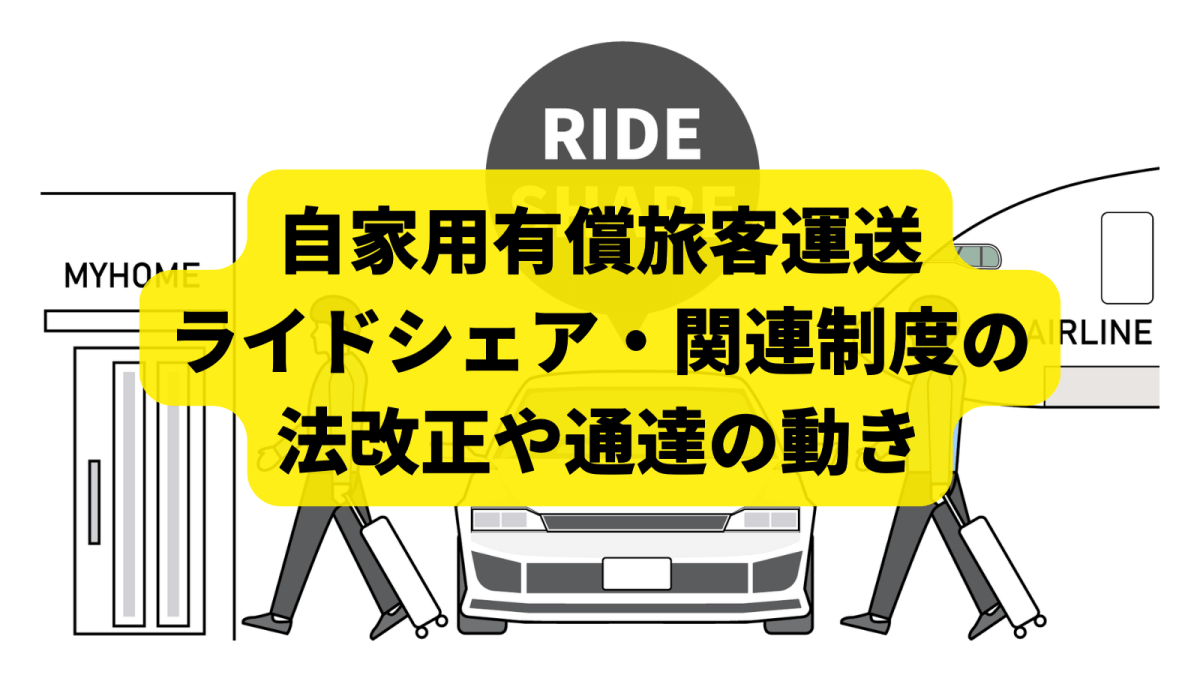この記事は随時更新を行っております。常に最新情報をお届けできるように努めます。
自家用有償旅客運送(福祉有償運送・交通空白地有償運送)や訪問介護員等による有償運送、自家用車活用事業(日本版ライドシェア)や、介護保険制度・障がい福祉サービスの制度変更、道路交通法・道路運送車両法などの関連する制度を含めた、法改正や通達の動きに関する情報提供を行っています。
併せて、全国移動サービスネットワーク様の「法制度の動き」のページもお読みください。
2025年
2025年4月
無人バス・タクシーに資金支援 政府、全国10カ所で(2025年4月18日・日本経済新聞)
政府は、企業や自治体が無人のバスやタクシーの事業を展開しやすくするよ支援します。ドライバーが不要なレベル4の自動運転車を対象に、全国10箇所での車両調達や交通インフラの整備にかかる費用を補助します。
副業で市職員約30人を募集へ タクシー不足解消に向けた「ライドシェア」 大分県別府市(2025年4月17日・FNNプライムオンライン)
大分県別府市で、タクシー不足の解消に向けて第3弾となるライドシェアに向けて、副業という形で市職員からも30人程度ドライバーを募ることになりました。
名称は「湯けむりライドシェアGLOBAL」で、配車アプリ「Uber」や「GO」を利用して配車する仕組み。
タクシーなどの普通2種免許、最短取得日数を半減へ 運転手不足受け(2025年4月17日・朝日新聞)
警察庁は17日、タクシーなどの運転に必要な普通2種免許を取得するための教習時間を減らし、最短6日間から3日間に変更する方針を決めました。運転手不足に悩むタクシー業界などから教習時間の短縮要望が出ていました。普通2種の教習時間は、学科19時限・技能21時限の計40時限ですが、学科2時限・技能9時限分を減らして、計29時限にします。
警察庁は5月17日までバブコメを実施したうえで、道路交通法施行規則を改正し、9月1日の施行を目指します。
高松市でタクシー配車アプリが本格運用 電脳交通など(2025年4月15日・日本経済新聞)
香川県タクシー協同組合と配車システム開発の電脳交通(徳島市)は、15日にタクシー配車地域アプリ「香川Taxi」の本格運用を高松市で始めました。香川Taxiでは、高松タクシー協会に加盟する事業者15社と個人タクシー事業者が参画し、合計257台の車両がアプリでの共同配車に対応します。利用者が複数のタクシー会社から車両を選択できるほか、配車可能な車両がない場合でも空車予測に基づいた予約が可能です。
クルーズ船の寄港急増で白タク行為も横行…タクシー不足も顕著に 解決策は? 乗船客”限定”のライドシェア始まる(2025年4月15日・FNNプライムオンライン)
国内有数のクルーズ船の寄港地となりつつある静岡の清水港。ただ、周辺ではタクシー不足が問題となっています。この問題を解決しようと、タクシー配車事業などを手がける一般社団法人静岡TaaS(静岡市葵区)が市に国への申請を働きかけ、17台分のライドシェアが許可されました。静岡交通(静岡市駿河区)に2台登録し、4月にサービスを始めました。
大和自動車、個人タクシーと提携し台数維持 第1号公開(2025年4月14日・日本経済新聞)
大和自動車交通は14日、個人タクシーと提携して自社のマークや無線機器などを使ってもらう取り組みで第1号となる事業者を報道公開しました。同様の試みは、国際自動車や日本交通が先行しています。提携では、個人タクシー事業者が売上の一部を大和自動車に支払う代わりに、同社のマークや無線機器、車両整備の施設が使えます。
タクシー継続に高齢者ら安堵 函館・南茅部地区、30年3月まで特例運行(2025年4月13日・北海道新聞)
タクシー営業の空白地だった函館市南茅部地区で、函館第一交通が2020年度から行う特例運行が、30年3月末まで継続される見通しとなりました。特例は1年おきに北海道運輸局の認可が必要でしたが、これまでの実績が認められ本年度から5年間の営業が可能な制度に移行しました。
維新 ライドシェアを全面的に導入するための法案 国会に提出(2025年4月11日・NHK)
日本維新の会は、一般ドライバーが有償で人を輸送するライドシェアを全面的に導入するための法案を国会に提出しました。この法案は、日本維新の会が単独で衆議院に提出したとのことです。
この法案では、タクシー事業の許可を得ていなくても、地域や期間を限定せずにライドシェア事業を行うことができるように、政府に法制上の措置を講じることを義務づけるとしています。
2025年3月
バスの運転手不足解消へ 福井県や市 職員が兼業で運転手に(2025年3月18日・NHK)
路線バスの運転手不足を解消しようと、福井県と福井市は今月から、県庁や市役所の職員が兼業でバスの運転手として勤務できるようにする取り組みを始めました。
相乗りタクシー、予約なしで即乗車 官民で試験運用(2025年3月17日・日本経済新聞)
国土交通省は、ANAホールディングスが出資する相乗りタクシー大手のニアミー(東京都中央区)と、乗客をリアルタイムでマッチングして予約不要の配車システムをつくります。今は原則として前日までの事前予約が必要です。2025年度にも都内で試験運用し、混雑時にタクシーがつかまりやすくなるか確かめるとしています。
ライドシェアドライバーがゆうパック配達 全国初の実証事業へ(2025年3月14日・朝日新聞)
石川県加賀市とUber Japan、日本郵便は、公共ライドシェアのドライバーがゆうパックを配達する「貨客混載」の実証事業を今月中に始めます。国内初の取り組みで、ドライバーの空き時間を有効活用することで、収入増加と稼働率の安定化が期待されるといいます。
なお、Uberアプリでのライドシェア業務は従来通り、加賀市観光交流機構とドライバー間の契約で運用します。ゆうパックの配達は、日本郵便がドライバーと契約し、「ラストマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可」を取得した上で実施するとのこと。
「運転免許証&“マイナンバーカード”」まもなく一体化!「免許更新の講習」オンラインで完結!? 所持しないと違反?話題の「マイナ免許証」のメリット・デメリットとは(2025年3月9日・くるまのニュース)
3月24日からマイナンバーカードを免許証(マイナ免許証)として利用できるようになります。
種別としては従来の免許証のみ・マイナ免許証のみ・従来の免許証とマイナ免許証の両方の3種類が使用可能です。運転する際には、従来の免許証またはマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。マイナ免許証の選択はあくまで任意ですが、利用する際には運転免許センターまたは警察署にて、マイナンバーカードのICチップ内に免許証情報を記録する必要があります。市役所では手続きできないので注意が必要です。
マイナ免許証に変更するメリットは、住所変更が自治体に届け出るだけで完了したり、免許更新時に優良運転者講習・一般運転者講習を受ける際はオンライン講習が受講可能になります。しかし、デメリットも存在します。運転免許証の有効期間がマイナ免許証の券面には表示されないため、有効期間などがアプリ等を経由して確認しなければならなかったり、有効期間切れ(うっかり失効)に気を付ける必要があります。また、マイナンバーカード自体の電子証明書の更新と、運転免許証自体の更新はそれぞれ別にあるので注意が必要です。そのほか、従来の運転免許証であれば最短で即日再交付が可能ですが、マイナンバーカードを紛失した場合の再発行には日数がかかります。
また、レンタカーでは対面での運転免許情報の確認を行うことができる(ただし、利用者側がマイナンバーカードを用意し、利用者自身のスマートフォンにマイナ免許証読み取りアプリの事前インストールを行うことが必要)ので問題ありませんが、いわゆる対面ではないカーシェアリングの場合には対応が難しいため、当面は従来の免許証が必要となります。
また、トヨタ自動車などがモバイル運転免許証を使った日本初の実証実験を始める動きもあります。モバイル免許証は偽造が難しく、免許証を搭載したスマートフォンを専用機器で識別し、本人が運転可能かどうかを自動的に判定します。レンタカーなどの利便性向上につなげます。
マイナ免許証についての詳細は、警察庁や警視庁のホームページでも調べることができますが、Yahoo!くらしのホームページにわかりやすく記載されています。
新潟・湯沢町で「日本版ライドシェア」 3月10日から(2025年3月7日・日本経済新聞)
新潟県湯沢町は7日、町内のタクシー事業者が「日本版ライドシェア」を3月10日から始めると発表しました。上越新幹線などで訪れたインバウンド(訪日外国人)を含む観光客らの移動の足を確保し、利便性を高めます。
根室のタクシー24時間営業、再開遠く 運転手不足深刻、7割が60代以上(2025年3月6日・北海道新聞)
北海道根室市内で、タクシー会社の24時間営業の再開が難航しています。日曜日から木曜日の深夜にタクシーを使えない状態が1年以上続いています。市はタクシーの夜間運行に、最大500万円の補助制度を創設しましたが、運転手不足が深刻となり、再開は見通せない状態です。
Uber、ライドシェアに加え「ゆうパックの配達」のダブルワークが可能に(2025年3月6日・自動運転ラボ)
ライドシェア×貨物配送という、興味深い取り組みが石川県加賀市で始まりました。同市と日本郵便、Uber Japanによる公共ライドシェアドライバーによる貨客混載の実証事業です。
自家用有償旅客運送(交通空白地有償運送)はもちろん、自家用車活用事業(日本版ライドシェア)も副業としては中途半端な印象が拭えませんでしたが、貨物配送業務を兼務することで、ドライバー職としての魅力を増します。
夜のタクシー「5分内乗車を」 年度末の台数不足解消へ 柏崎市が啓発(2025年3月5日・読売新聞)
新潟県柏崎市は、夜間のタクシー利用時に「到着後5分以内の乗車」を新たなマナーにしようと啓発しています。夜間のタクシー台数は日中の半数ほどに減少し、需要に対応できなくなりつつあることが背景にあります。
QRコード読み込みタクシー予約 両備 観光客や訪日客の需要見込む(2025年3月4日・山陽新聞)
両備グループ(岡山県岡山市)は、岡山県内の観光地やホテルに掲げた専用のQRコードをスマートフォンでよみこむだけで、タクシーの予約ができる新たなサービスを始めました。
高齢者や障害者らのタクシー利用、何度でも1回300円…愛知・みよし市(2025年3月1日・読売新聞)
愛知県みよし市は4月から、路線バスなどの利用が困難な高齢者や障害者などを対象に、1回300円で無制限にタクシーを利用できる「おでかけタクシー運行事業」をスタートさせます。高齢者を対象にタクシーのチケットを配布するなどしている自治体はありますが、定額で無制限に利用できるのは珍しい。
お墓参りサポートタクシー開始 松山観光バス 庄内エリア対応 墓参り代行サービス(2025年3月1日・荘内日報社)
貸し切り観光バスやタクシーなどを運行する松山観光バス(山形県酒田市)が、県外在住や自身の高齢化などを理由に、先祖の墓参りが難しい人に向けたサポートサービス「お墓参りサポートタクシー(墓サポ)を開始します。タクシー運転手が墓石の清掃・合掌を代行するサービス。
2025年2月
運賃値上げ、国裁量認める タクシー会社の訴え退ける(2025年2月27日・日本経済新聞)
最高裁判所は、関東運輸局による運賃値上げに対して反対する、東京都内のタクシー会社「ロイヤルリムジン」など2社が、値上げを強制されないよう一時的な差止めを求めた裁判で、国の裁量を認め、タクシー会社側の申し立てを退ける決定をしました。法廷では「事業者は運賃の設定に一定の制約を受けることを当然に予定している」とした上で、運輸局の運賃設定は「事業者の営業上の利益を踏まえており不合理ではない」とした。
JR東日本が「ライドシェア」 交通補完、千葉や秋田で実証運行(2025年2月26日・47NEWS)
JR東日本は、一般ドライバーが自家用自動車で客を運ぶ「ライドシェア」への参画を見据え、実証運行を始めます。千葉県南房総市と館山市で今年3月にも実施するほか、秋田県仙北市では今年後半の開始を検討しています。全国的に公共交通機関が脆弱になる中、生活の足を公共ライドシェアで補完します。運行主体は自治体。
JR東日本は、ドライバーとなる社員を派遣し、グループ会社が持つ車や待機場所の提供などを行います。
新興ニューモが挑むライドシェア革命 買収で規制破る(2025年2月26日・日本経済新聞)
一般ドライバーが有償で乗客を送迎する「日本版ライドシェア」は、タクシー会社しか参入することができません。
この規制に挑むのがnewmoで、スタートアップながら豊富な資金力でタクシー会社を買収し、事業拡大をしています。利便性を向上させて、将来の全面解禁への機運を高めます。
ロボタクシーが都心を走る 新技術の社会受容がカギに(2025年2月23日・日本経済新聞)
運転席が無人のクルマが東京の街を行き交う。そんなSFチックな夢物語を、タクシー大手、日本交通の取締役で配車アプリGOの会長を務める川鍋一朗氏は、いたって本気です。Waymo(ウェイモ)と組んで、自動運転車両を25台導入し、都心7区から実証実験を始めます。
タクシー、都市部で時限増車 ライドシェア普及せず不足(2025年2月19日・日本経済新聞)
国土交通省は、タクシーの台数増加を規制している地域で、時限的な増車を認めます。東京23区などの、全国およそ60の営業区域で、稼働していない車両の一部を、運転手が足りている他社が運行できる制度。
一般ドライバーが有償で乗客を運ぶ「日本版ライドシェア」の普及は限定的なため、運行台数を維持するために政策を転換します。
訪問介護の支援、事業所の協働化に最大200万円補助 厚労省 人材確保の広報や研修にも(2025年2月12日・介護ニュースJoint)
厚生労働省は、今年度の補正予算で訪問介護事業所への新たな支援策を講じます。たとえば、人材の一括採用、合同研修会の実施、ICTインフラなどです。
小規模法人等の協働化・大規模化の取り組み支援、その他そういった協働化・大規模化に取り組んでいない事業所も支援します。たとえば、人材・利用者確保のためのホームページ開設・改修・広告(パンフレット・チラシ等)の作成印刷や、新人ヘルパーの利用者宅同行支援・登録ヘルパーの常勤化などが補助対象となります。
住民マイカーを地域の足に 広まる公共ライドシェア 静岡知事も推進(2025年2月12日・朝日新聞)
住民や観光客の移動手段が乏しい交通空白地を解消する手段として、「公共ライドシェア」が期待を集めています。一般ドライバーがマイカーなどで有償で旅客を運ぶ仕組みですが、「ライドシェア先進県」を目指して静岡県も前向きな自治体を後押ししています。
AIが予約状況から最適ルート割り出す乗り合いタクシー、山口県田布施町で実証運行…月3500円の定額制(2025年2月12日・読売新聞)
山口県田布施町はAI(人工知能)を活用した、予約制の乗り合いタクシー(愛称「のりーね」)の約1年間の実証運行を始めました。白ナンバー車を使用していますが、交通空白地有償運送として実施しています。
実施主体は田布施町で、運行は町の委託を受けた町内のタクシー会社が行い、乗客は最大で6人まで乗せることができます。予約状況からAIが効率的に複数人が乗車できる最適なルートを割り出し、運転手が送迎します。AIは島根県の交通コンサルタント会社「バイタルリード」のシステムを活用。
利用できるのは町内の在住者で、事前登録が必要。料金は月額3,500円(口座引落)。
月収100万円超 第一交通、新潟→白馬村に運転手派遣(2025年2月10日・日本経済新聞)
タクシー大手の第一交通産業は、全国屈指のスキーリゾート地として知られる長野県白馬村で急増するインバウンド(訪日外国人)の移動需要に対応するため、隣県の新潟から運転手を派遣する施策を始めました。白馬村では、1ヶ月の手取り額が100万円を超える運転手も出ているとのことです。
タクシー業の廃業等、過去最多!「自動運転化」で追い打ちか(2025年2月10日・自動運転ラボ)
帝国データバンクによると、2024年に発生した負債1000万円以上のタクシー業の倒産・廃業件数は82件となり、過去最多となりました。
ドライバー不足も大きな要因となったようです。タクシー業界は日本版ライドシェアで急場をしのいでいますが、中長期的にはさらなる追い打ちが待ち受けています。それは自動運転タクシーの登場です。ドライバーに依存しない自動運転車は、業界の構造を大きく変える可能性があります。
(プレスリリース)あいおいニッセイ同和損保、GOとの連携で国内ライドシェア事業の実態・ニーズに対応する新たな保険商品をリリース(2025年2月7日・@niftyニュース)
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社は、タクシーアプリ「GO」を運営するGO株式会社と連携し、ライドシェア事業向け自動車保険「移動支援サービス事業用自動車保険特約」において、2025年4月より保険を改定し、「小額の車両損害を補償するプラン」、「勤務形態に応じた1時間単位の保険料設定」などの提供を開始します。
- 保険料1時間単位型:短時間勤務の場合、1日単位の保険料では割高感(負担)がある
- 1時間単位型の保険料上限:1時間単位で保険料が変動すると長時間運行の場合、保険料が高くなる
- 車両補償10万円限度プラン:夜間運行中の酔客の嘔吐による車内汚損事故等の少損害を補償する
- 1日単位型の移動支援サービス提供日数のカウント方法を、現行の0時~24時から16時~翌16時を追加。
- 補償対象車両に、レンタカー・カーシェアリングを追加(カーシェア等でライドシェアを実施したい場合に対応)。
ウーバー配車、27年までに47都道府県で 電脳交通と提携(2025年2月6日・日本経済新聞)
Uber Japanは2027年までにタクシー歯医者サービスを47都道府県で利用できるようにすると発表しました。タクシー会社の電脳交通(徳島市)と連携して、同社の歯医者システムを使う全国のタクシー会社に広げます。
Uberのタクシー配車は2月時点で19都道府県で利用でき、電脳交通のシステムは全国47都道府県の約600社・計2万台程度のタクシーで導入されています。Uberアプリでの配車依頼を電脳交通のシステム画面で運転手に通知するとのこと。
南房総地域の交通空白解消へ 公共ライドシェア実証運行 夜間~早朝 3月から、JR東協力(2025年2月4日・千葉日報)
運転手不足により、既存の公共交通機関の維持が困難となる中、南房総市と館山市は、市町村(自治体)が主体となり、一般ドライバーが有償で乗客を運ぶ「公共ライドシェア(交通空白地有償運送)」の実証実験を2025年3月から始めます。
Googleも注目?茨城交通、「完全自動運転バス」展開なら世界的快挙に(2025年2月3日・自動運転ラボ)
茨城交通や、先進モビリティらが取り組む自動運転バスが、特定自動運行許可を取得しました。ひたちBRTのバス専用区間6.1kmで、2025年2月からレベル4運行を行います。中型バスのレベル4(特定エリア内における完全自動運転)による特定自動運行は国内初で、運行区間も国内最長距離とのこと。
国内はもちろん、世界における自動運転バスの大半は小型モデルで、中型サイズの自動運転化は世界的にもまだまだ珍しい。
海外旅行者人気で観光が潤う「小豆島」がピンチ!自動運転バスが救世主となるか?(2025年2月1日・WEB CARTOP)
香川県の小豆島にある土庄町ですが、人口は1.2万人(2020年国勢調査)。
小豆島全体が観光地として認識されていることもあり、海外からの観光客が増加傾向にあるそうです。同町もその恩恵を受けているものの、人口減少には歯止めがかかりません。1970年は人口2.2万人であったから、半世紀で1万人ほど減少し、少子高齢化が加速しています。
少子高齢化が進んで、運転免許証の返納者も増加しています。そのため、公共交通機関が必要となっていますが、深刻なドライバー不足が起きています。上記の背景から2024年9月12~17日の6日間、自動運転バスの実証実験を町内の公道で実施しました。
この実証実験は、「20年先の小豆島をつくるプロジェクト」の第2弾に位置付けられています。第1弾は「シェアサイクル事業」で、今後はAIによる自律運行無人ボートの導入に向けた実証実験のほか、言葉の壁を解消するAI翻訳機の導入などが検討されています。同島は観光客が増加傾向にあるものの、来島者の約7割が宿泊しておらず、経済効果が限定的になっていましたが、宿泊施設の老朽化・キャパシティ不足、飲食店の不足、二次交通の脆弱性といった問題を解消することを目指します。
2025年1月
群馬・桐生市のライドシェア「先進的な配車システム」 国交省が評価(2025年1月31日・上毛新聞)
群馬県桐生市で昨年11月に日本版ライドシェア運行が始まったことを受け、国土交通省 物流・自動車局旅客課の重田裕彦課長や関東運輸局の担当者が30日、桐生市役所を訪れて、荒木恵司市長や沼田屋タクシーの小林康人社長と懇談しました。同社独自の配車システムについて、重田課長は「これほど簡便な仕組みのものは、知る限り全国でもあまりない。先進的なものとしてPRしていきたい」と評価しました。
医療的ケア児 福祉タクシーで保護者付き添いなく通学 モデル事業はじまる 鹿児島(2025年1月28日・TBS NEWS DIG)
鹿児島県は、医療的ケアが日常的に必要な「医療的ケア児」について、看護師が同乗するタクシーで学校に送迎する試みを始めました。
医療的ケアは、たんの吸引や人工呼吸器を付けるなど、医療的ケアが日常的に必要な子どもで、スクールバスでの通学が難しく、保護者による送迎が大半です。
スクールバスが利用できず、保護者による送迎が必要な医療的ケア児は県内におよそ130人。県は将来的に通学支援を県内全域で実施したいとしています。
【沖縄県那覇市・豊見城市・名護市・国頭村】移動費が節約できる女性専用ライドシェアサービス「Wely」の実証実験がスタート(2025年1月28日・@niftyニュース)
沖縄県内4地域(沖縄県那覇市・豊見城市・名護市・国頭村)で女性専用ライドシェアサービス「Wely」の実証実験が1月末~2月上旬の期間にスタートします。コンセプトは「乗せて」と「乗せてってあげる」がつながり、一緒に移動することでお互いに移動費が節約できる“ゆいまーる”なライドシェアサービスとのこと。
利用料金は移動にかかる実費費用のみ(ガソリン代や高速代・専用保険代)とのことで、許可又は登録を要しない運送。
損保ジャパンなどがライドシェア保険、自治体やNPOに(2025年1月27日・日本経済新聞)
一般社団法人、全国自治体ライドシェア連絡協議会と損害保険ジャパンは、市町村やNPO法人等が交通空白地などで運送主体となる「公共ライドシェア」向けに専用保険の提供を始めました。「i-Chanライドシェア保険(移動⽀援サービス専⽤⾃動⾞保険(地域の移動を⽀える保険))」で、自治体など運行主体が契約し保険料を支払い、万一の事故の際に、ライドシェアの運行を行う運転者個人の契約する自動車の場合でも、個人の自動車保険ではなく、専用の保険で対応することが可能となります。
緑内障患者約6割“運転中の視野異常 自覚せず”眼科など調査で(2025年1月26日・NHK)
目の視野に異常が出る病気「緑内障」と診断されても、約6割の患者が運転中の視野の異常を自覚していなかったことが、都内の眼科などの調査で分かりました。
症状が進み視野が大幅に狭くなっていても異常に気付かない人もいて、調査した医師は「そのまま運転を続けると事故を起こすリスクが高まる。車を運転する人は眼科で検査を受けて目の状態を確認して欲しい」と呼びかけています。
キャンパスライフの不便解消へ 学生自ら“交通改革”に乗り出す 「乗り合い支援サービス」で移動手段を確保【秋田発】(2025年1月25日・FNNプライムオンライン)
秋田市郊外の雄和地区にある国際教養大学ですが、秋田空港から車で10分ほどのところに位置しますが、秋田市中心部に出かけるには車で約30分かかります。
学生の多くは車を持たず、バスや電車を乗り継いで移動しています。この課題解決に学生自らが取り組んでいます。車の乗り合いを支援するアプリケーション「Rideon(ライドオン)」の開発を進めています。
このアプリは「学内完結型の乗り合いマッチングサービス」で、運転手がどこかに行くときに、空いている座席を誰かとシェアしようという感覚から生まれました。学生の移動機会を増やしていこうという取り組み。
移動したい学生と車を持つ学生をオンラインで結びつけるこのサービス。ライバーはどこかに行く際に、行き先・時刻・乗車可能人数を登録し、そのデータから乗り手がリクエストを送信します。双方が合意の上、行き先を細かく設定して乗車するという仕組みです。
つくば市など4自治体、27日から交通空白域で「ライドシェア」(2025年1月25日・朝日新聞)
交通空白地域の住民などをマイカーで運ぶ「地域連携公共ライドシェア」が27日から茨城県つくば、土浦、下妻、牛久の4市で始まります。
公共ライドシェアは、4市が連携して実施する自家用有償旅客運送サービス。住民の買い物や通院、観光客の移動を公募に応じて登録したドライバーが担います。
指定された4エリアを運行する。予約制で、料金や運行時間はエリアによって異なり、他の客と相乗りになるケースもあります。
地域外から応援タクシーを派遣、『ニセコモデル』が好調(2025年1月25日・レスポンス)
エリア限定でタクシーが営業区域外旅客運送を行なう『ニセコモデル』が好調だそう。2年目となる2024年度は12月16日から2025年3月15日まで運行予定で、今シーズンは乗車実績を大きく改善しているとのこと。
「公共ライドシェア」県が立ち上げ支援 市町村公募、コーディネーター派遣(2025年1月23日・中日新聞)
愛知県は過疎地の移動手段を確保するため、市町村などが自家用車を使って有料で客を運送する「公共ライドシェア」の立ち上げ支援を2025年度から始めます。実施する地域を公募で3カ所ほど選び、専門のコーディネーターを派遣。運行形態や配車、勤務体制、料金など実施方法の確立を支援し、2年計画で実証実験の実施につなげます。
要介護者等通院送迎サービス「おちゃまるタクシー」の出発式を開催(PR TIMES)(2025年1月23日・毎日新聞)
静岡県内初の、地域の社会福祉法人と住民、市が連携した「福祉有償運送(愛称・おちゃまるタクシー)」を静岡県藤枝市が立ち上げました。
地域の足となる「おちゃまるタクシー」は、社会福祉法人(三愛会と富水会)が運送主体となり、デイサービスの福祉車両を使用しない時間帯に行う要介護者等の通院送迎サービスとなります。片道1,600円とのこと。
佐賀と武雄の「ライドシェア」実証実験 自治体関係者など視察(2025年1月23日・NHK)
自家用車を使って一般のドライバーが人を運ぶ、「ライドシェア」の実証実験が行われている佐賀市と武雄市を、国や全国の自治体の関係者が訪れ、取り組み状況などを視察しました。
この視察は、一般社団法人「全国自治体ライドシェア連絡協議会」が国土交通省の担当者や全国の自治体のトップなど150人余りを招いて行ったものです。
このうち、武雄市では、連絡協議会の担当者が去年11月からキッズサポートの一環で、山間部から市街地までを路線とし、学習塾や習い事に通う子どもたちを送り迎えしようと、住民どうしで送迎を支え合う「共助版ライドシェア(許可又は登録を要しない運送)」を導入したことを紹介しました。
北九州市などのタクシー運賃 今夏にも値上げの見通し(2025年1月22日・NHK)
九州運輸局は、北九州市などのタクシー運賃について値上げが必要だと判定し、ことし夏にも実際に値上げされる見通しになりました。
燃料費の高騰や運転手の労働環境の改善などが理由で、運輸局によりますと、事業者側はいずれも普通車で、現在770円の初乗り運賃を810円から970円に引き上げ、初乗り以降の加算距離については、現在の280メートルを240メートルから258メートルに見直すよう求めているということです。
タクシー業界が管理するから日本版ライドシェアが普及しない!日野がライドシェア問題に乗り出した(2025年1月11日・WEB CARTOP)
日野自動車が自家用有償旅客運送の運行管理受託サービスの拡充に向けた実証実験を開始しています。
従来から自治体ライドシェアについては日野自動車がこれまで培ったバスやトラックの知見を活かした運行管理受託サービスを展開してきました。およそ1年が経過したことから、新たなサービスへと進化させるための実証実験を開始したのです。
これは通信型のドライブレコーダーを用いることで、運行管理を効率化しているのが特徴。GNSS(GPSを含む人工衛星による全地球航法衛星システム)により、車両の走行状況を運行管理者がリアルタイムで把握できるほか、運転の質や安全性も判断することができて、作成するのが面倒な日報も自動作成してくれるなどが強み。
日野自動車の運行管理システムであれば、タクシー会社ほどの手数料を必要とせず、運行管理が行えるから、ユーザーにはもっと手軽な料金で、そしてドライバーの利益率も向上するに違いありません。
白浜町の乗り合いバス運行打ち切りで行政処分 近畿運輸局(2025年1月10日・NHK)
白浜町の乗り合いのコミュニティーバスの運行会社が一部の路線を終点まで運行せず途中で切り上げていたとして、国土交通省近畿運輸局はバス1台を10日間使用停止とする処分にしました。
運送×タクシー×旅行会社がタッグ組みライドシェア参入 人手不足や市場縮小など共通する課題解決の一手に 永平寺町で11日スタート(2025年1月10日・FNNプライムオンライン)
タクシーの供給不足の解消を目的に、福井県内でも2024年9月から始まった日本版ライドシェアですが、この日本版ライドシェアを市場縮小・働き方改革・観光振興といった企業や地域の課題解決に活用しようという取り組みが、1月11日から永平寺町で始まります。
永平寺町で始まるのは、日本版ライドシェアを活用した観光タクシーツアー。
町内の運送会社・日本商運とタクシー会社・松岡交通、大手旅行代理店・JTBの3社による取り組みで、福井駅を起点に、大本山永平寺や酒蔵など永平寺町内の主要観光地を巡ります。車両の提供は松岡交通、ドライバーは日本商運の社員が担い、ツアーはJTBが販売します。
2024年
2024年12月
JR東日本、ライドシェア本格参入へ…千葉や秋田の「交通空白」地域で社員やOBがドライバーに(2024年12月21日・読売新聞)
JR東日本は、一般ドライバーが乗客を送迎する「ライドシェア」事業に本格参入する方針を固めました。自社の社員やOBをドライバーとし、タクシーの稼働台数が少ない時間帯に運行する。タクシーやバスを利用しにくい「交通空白」の解消につなげます。
自治体が運行を管理する「公共ライドシェア」の枠組みで実施するとのことです。
2024年度中に、千葉県南房総市や館山市で運行を始められるよう調整。午後10時~翌朝7時に運行し、専用のアプリで呼べるようにすることを検討。車両はグループ会社のレンタカーを使うとのこと。
広がるか、ケアマネの保険外サービス 厚労省が書類作成や郵便受取、救急車同乗を「対応し得る」と整理(2024年12月16日・介護ニュースJoint)
ケアマネジメントの課題と向き合う検討会を今年春から開催してきた厚生労働省は、これまでの議論をまとめた報告書(中間整理)を12日に公表しました。
利用者・家族のニーズに応える努力の結果として大きく広がったケアマネジャーの業務を、大きく4つに分類。法定業務の範囲を超えているものを、「保険外サービスとして対応し得る」「他機関につなぐべき」などと初めて位置付けました。
大阪でライドシェア24時間運行 万博期間、政府容認へ(2024年12月13日・日本経済新聞)
2025年国際博覧会(大阪・関西万博)でのタクシー不足に備え、国土交通省が「日本版ライドシェア」の規制を大阪府内で大幅に緩和する方針を固めたことが13日分かりました。2025年4~10月の万博会期中、従来の週2日計約12時間の制限を撤廃し、常時運行できるようにします。近く大阪府・市などと会議を開き、正式に決定します。
運行の主体となるのはタクシー事業者です。
神奈川版ライドシェア、本格実施ならず「試行運行」に 市議会で異論(2024年12月13日・朝日新聞)
神奈川県三浦市が実証実験をしている「神奈川版ライドシェア」(愛称・かなライド)で、実証実験終了後の今月17日から予定していた本格実施が「試行運行」に変更されました。市議会などから本格実施に異論が出たためです。
市が10日、試行運行の概要を発表し、市地域公共交通会議に書面決議を求めました。今年度いっぱいは従来通り市が実施主体となってタクシー会社が運行管理する方法を続け、試行運行期間中に必要な見直しを検討するといいます。
東広島のタクシー会社 定期点検記録偽造などで事業許可取消(2024年12月12日・NHK)
東広島市のタクシー会社が実際には行っていなかった定期点検(法定点検)の記録を偽造するなど繰り返し法令に違反したとして、中国運輸局はこの会社の事業許可を取り消す処分を行いました。
ホンダ GMと共同で計画 自動運転タクシーサービス 中止へ(2024年12月11日・NHK)
ホンダはアメリカの自動車大手、GM=ゼネラルモーターズが完全自動運転のタクシー事業から撤退することを受けて、GMと共同で2年後に日本で始める予定だった自動運転タクシーのサービスを中止することになりました。
ライドシェア参入要件を緩和 バス・鉄道対象に国交省(2024年12月2日・共同通信)
国土交通省は、一般ドライバーが自家用車で客を運ぶ「日本版ライドシェア」の普及に向け、バス・鉄道事業者を対象に参入要件を緩和することとしました。すでに旅客運送に必要な体制が整っているため、参入の前提となるタクシー事業の許可を得やすくします。2日の審議会部会で明らかにしました。
現状は、日本版ライドシェアはタクシー事業者だけが運行できます。
上記の内容変更が行われたとしても、バス・鉄道事業者は、まずタクシー許可を取得した上で日本版ライドシェアを実施する形となるのがポイントです。
2024年11月
二本松でライドシェア 福島県内初、平日・日中の「空白」解消へ(2024年11月29日・福島民友)
福島運輸支局は28日、一般ドライバーが自家用車やタクシーの遊休車両を使い、有料で客を運ぶ「日本版ライドシェア」に関して、二本松市の昭和タクシーに許可を出したと発表しました。許可は県内で初めてです。
「原付きバイク」125cc以下も来年4月から対象拡大へ(2024年11月13日・NHK)
警察庁は、「原付きバイク」について現在の総排気量50cc以下のもののほかに、総排気量125cc以下で最高出力を制御し、速度を抑えたものも加えて、原付き免許などで運転できるようにする運用を、来年4月から始めることを決めました。
最高出力が制御され新たに原付きバイクに加えられたものについては「二段階右折」などの原付きバイクの交通ルールが適用されることになります。
一方、最高出力が制御されていない125cc以下のバイクの運転には引き続き、小型限定普通二輪免許以上の免許が必要になります。
京都府大山崎町、バス実証実験で道交法違反疑いか 運賃払うなら不要になる使用義務とは(2024年11月10日・京都新聞)
京都府大山崎町が実施している町営バスの実証実験で、町が道路交通法に反してチャイルドシートを使わずに6歳未満の乳幼児を乗車させていたとのこと。
有償運送であれば、チャイルドシートの使用義務が免除となります。
視覚障害の同行援護サービス提供責任者の要件緩和 厚労省、人材確保しやすく(2024年11月3日・福祉新聞)
厚生労働省は視覚障がい児・者の移動を支援する「同行援護」のサービス提供責任者の要件を緩和します。
同行援護従事者養成研修一般課程を修了し、視覚障害者の介護などの実務経験が3年以上あることを新たに加え、同行援護従事者養成研修応用課程を修了すれば、責任者として従事できるようにします。
10月22日の社会保障審議会障害者部会と、こども家庭審議会障害児支援部会の合同会議で委員から合意を得ました。通知を改正して来年4月に施行します。
2024年11月1日より、自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!(政府広報オンライン)
道路交通法が改正され、2024年11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用しながら「ながら運転」を行った場合の罰則が強化され、また「自転車の酒気帯び運転」も新たに罰則対象となります。これまで、飲酒運転については酩酊状態で運転する「酒酔い運転」が罰則対象でしたが、自動車と同様に酒気帯び運転や、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止となります。
- ながらスマホ(ながら運転)について
- 現行:5万円以下の罰金
- 改正後1:6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金に改訂(変更)
- 改正後2:交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
- 飲酒運転について
- 現行:酒酔い運転の場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 改正後1:酒気帯び運転(アルコール0.15mg以上)の場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 改正後2:飲酒運転する者に自転車提供した場合、自転車の提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 改正後3:飲酒運転する者に酒類提供した場合、酒類提供者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金
- 改正後4:飲酒運転している者の自転車に同乗した場合、同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金
傘差し運転、イヤフォンやヘッドフォンを使用し音が聞こえない状態での運転、2人乗りについては、従来通り5万円以下の罰金です。並進運転は2万円以下の罰金または科料です。
また、従来より危険な違反行為を繰り返すと、自転車運転者講習の対象になりますが、「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」についても、今回の道路交通法改正に伴い、自転車運転者講習の対象になります。命令を無視して自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金となります。
詳細につきましては、政府広報オンラインの記事にて紹介されています。
2024年11月1日施行の改正道路交通法で、「モペットはバイク」と明記
ペダル付き原付き自転車「モペット」は、たとえペダルをこいで走行してもバイクに分類されることとなり、運転にはヘルメットや免許証が必要となるルールを明記した改正道交法が1日に施行されました。
2024年10月
国交省、「貨物版ライドシェア」浮上 宅配・タクシー 運転者不足解消へ 事業化可能性を年内実証 繁忙期有償運送 制度柔軟化も検討(2024年10月29日・物流ニッポン)
国土交通省が21日開催したドライバーシェア推進協議会で、タクシー事業者を実施主体に、一般ドライバーが自家用車で乗客を有償で運ぶ日本版ライドシェア(自家用車活用事業)の手法による宅配での活用案が浮上しました。タクシーと宅配の両事業でのドライバー不足の解消に向け、年内にも実施するドライバーシェアの実証実験で、タクシーによる宅配、宅配車両での旅客運送を含め、事業化の可能性や法令・制度上の課題について検証する見通しです。
「城崎温泉」で免許不要で歩道を走れる近距離モビリティ「ウィル」移動サービス開始 観光客の移動、坂道やデコボコ道も支援(2024年10月25日・ロボスタ)
城崎温泉街でユニバーサルツーリズム事業などを展開する「NPO法人ぷろじぇくとPlus」とWHILL株式会社は2024年11月5日より、近距離モビリティ「WHILL」(ウィル)の移動サービスを開始することを発表しました。
料金の目安は1泊2日で7,000円、4時間までなら5,000円、8時間までなら6,000円程度を設定している。豊岡市観光公式サイトから申し込みができます(要予約)。
WHILLは電動車いすで、道路交通法上では歩行者扱いとなります。
【三浦市】神奈川版ライドシェアの新たな要望書提出(2024年10月24日・湘南人)
神奈川県三浦市では、夜間のタクシー不足問題に対処するため、「神奈川版ライドシェア」の実証実験を実施中です。2024年10月23日、同市と神奈川県は、この実証実験で得られた成果をもとに行政に新たな要望書を提出しました。
三浦市では市が主体となってライドシェアの実証実験を2024年4月17日から行っています。これまでに600回以上の利用があり、事故やトラブルもなく、安全に運行されています。
現在は公共ライドシェア(交通空白地有償運送・三浦市が運送主体で、タクシー会社が協力する事業者協力型)として運用されており、その場合は雇用契約の有無は特に問われないため、市と運転者が業務委託契約を結ぶこととなっています。しかし、将来的にタクシー会社が運送主体となる日本版ライドシェア(自家用車活用事業)に移行する際に、現在は日本版ライドシェアでは許可申請書に「自家用車ドライバーとの契約形態」の記載欄があり、特に制約がないように思えるが、実際には「自家用車活用事業は雇用契約ではないと、安全面で疑義が生じる」と運輸局では回答されているようです。
“加賀版ライドシェア”開始から半年あまり…ドライバーを対象に安全講習会を実施(2024年10月22日・FNNプライムオンライン)
公共ライドシェア(交通空白地有償運送)で、一般ドライバーがお客様を目的地まで送り届ける加賀市版ライドシェア向けの安全運転講習会が、加賀市内の自動車学校で開かれました。この講習会は加賀市でライドシェアの配車を手がけるUber Japanと運行を管理するタクシー会社などが企画しました。
加賀市版ライドシェアは、今年の3月12日に運行開始し、これまで554件の利用があったとのことです。
リゾート地もタクシー不足 長野で「公共ライドシェア」実証実験へ(2024年10月16日・毎日新聞)
JR東日本などは11月1日から「公共ライドシェア」の実証実験を長野県野沢温泉村で始めます。全国有数のリゾート地として知られる野沢温泉村でもタクシー不足が社会問題化しており、地元観光団体などと共同で、観光客や地域住民の足としての活用を検証します。
2024年11月1日から2025年1月31日まで「野沢温泉村内での公共ライドシェアの実証実験」を実施し、一般ドライバーを10人程度募集予定で、「のざわ温泉交通株式会社で採用します」とのことですが、公共ライドシェア(交通空白地有償運送)の方式を採用するため、運送主体は一般社団法人野沢温泉マウンテンリゾート観光局となり、事業者協力型自家用有償旅客運送で、協力事業者がのざわ温泉交通株式会社となるようです。
配車アプリは国産アプリのNearMeを活用。電話でも配車申込みを受け付けます。
鉄道等の公共交通機関の遅延時における自家用車活用事業の活用について(2024年10月11日・国土交通省)
荒天や事故等により鉄道等の公共交通機関に遅延や運転見合わせが生じた場合、鉄道およびバスによる代替輸送やタクシーによる機動的な輸送が行われていますが、輸送サービスを円滑に提供するため、関係者間の連絡体制を構築するとともに、必要に応じて地方運輸局などが道路運送法第20条第1号に基づき営業区域外運送が可能であることをタクシー事業者団体にアナウンスします。また、その際に自家用車活用事業(日本版ライドシェア)による地域の一般ドライバーを活用した運送を行うことも可能とします。
自賠責の保険証、スマホ保管もOK…国交省が11月にも電子証明書の交付開始(2024年10月7日・読売新聞)
国土交通省は、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の保険証をスマートフォンなどの電子媒体で保管できるようにする方針です。現在は法令で車内での保管がドライバーに義務づけられていますが、電子媒体を用いれば紙の保険証の備え付けは不要になります。
こちら(PDF証明書)についての詳細は、一般社団法人日本損害保険協会様のホームページに詳細が解説されています。
新たに自賠責保険に加入すると、紙面タイプの自賠責保険証明書が保険会社より発行されますが、紙面タイプの証明書右下に印刷されたQRコードをスマートフォンで読み取ると、パスコードの入力画面が表示されます。パスコードはQRコード横に印字されている数字で、パスコードを正しく入力するとPDFデータをダウンロードすることができます。
紙面タイプの証明書発行を行わず、PDFの自賠責保険証明書のみを希望することも可能で、その場合の保険契約者は自賠責保険加入時にメールアドレスを入力します。そのメールアドレス宛に、証明書ダウンロードURLと、ダウンロードURLで必要となるワンタイムパスワードが送信されます。ダウンロードURLにアクセスし、そのパスワードを入力してPDFデータをダウンロードします(紙面はなく、ダウンロードされた証明書のみとなります)。
全国初、郵便集配車をタクシー代わりに バスない時間帯に片道1千円(2024年10月2日・朝日新聞)
タクシーの少ない農村部で、郵便局の集配車を高齢者の足として活用する「公共ライドシェア(交通空白地有償運送)」の実証運行が、北海道上土幌町で始まりました。集配車を使うのは全国初といいます。
「交通空白地」の解消を目指した、国土交通省による令和6年度の「共創・MasS実証プロジェクト」の一環。
町が主体となり、日本郵便に運行を業務委託し、2024年10月1日(火)~11月29日(金)の間、町の中心部から東に約3~12キロ離れた居辺地区の8世帯の高齢者を対象に実施している。事業費は約120万円とのこと。
平将明デジタル相、ライドシェア全面解禁に慎重姿勢 「スケジュールに沿って対応」(2024年10月2日・産経新聞)
石破茂内閣でデジタル相に就いた平将明氏は10月2日の就任会見で、ライドシェアにIT企業などタクシー会社以外の参入を認める全面解禁について、「基本的な方針が固まっているので、そのスケジュールに沿って対応したい」と慎重な姿勢を示しました。
全面解禁を認める法整備を巡っては、政府は今年の5月に期限を設けずに検討する方針を確認しており、道筋がついていない状況となっています。
運転手人材バンク 1日から受付開始 公共ライドシェア普及へ 茨城県南西4市、目標80人(2024年10月1日・茨城新聞)
茨城県のつくば、土浦、下妻、牛久4市が来年1月から取り組む運送事業「公共ライドシェア」で、4市は30日、運転手人材バンクへの登録受け付けを10月1日から始めると発表しました。
同事業では、オンデマンド型交通を手がける都内の会社のサービスを利用。2027年3月まで実施する予定です。運転手人材バンクの名称は「コミュニティ クルー」といいます。
運行では最適な配車や走行ルートを示す人工知能(AI)システムを使用。ドライバーには歩合給と運行回数に応じた報奨金が支払われるとのことです。
貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正(2024年10月1日公布・2025年4月施行予定)
近年、EC(電子商取引)市場規模の拡大により宅配便の取扱個数が増加しており、物流センターや小売店を介して消費者に荷物を運ぶ手段として、軽自動車による運送需要が拡大している一方、平成28年から令和4年にかけて、保有台数1万台当たりの事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数は、約5割増加している状況のため、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)等について所要の改正を行いました。
2024年10月1日に公布し、2024年11月1日に講習機関に係る登録開始、2025年4月に事業者に対する規制を実施(施行)予定です。
なお、1人で事業を行っている場合は、自ら実施してください。
- 貨物軽自動車安全管理者の選任と講習受講の義務付け(バイク便事業者を除く)
- 講習名は貨物軽自動車安全管理者講習(5時間)、貨物軽自動車安全管理者定期講習(2時間)
- 対面またはオンライン講習可
- 業務記録の作成・保存の義務付け(1年間保存義務、バイク便事業者を除く)
- 事故記録の作成・保存の義務付け(3年間保存義務)
- 国土交通大臣への事故報告の義務付け
- 特定の運転者への指導・監督及び適性診断の義務付け(バイク便事業者を除く)
- 特別な指導の詳細は、2024年10月中に国土交通省のホームページ上に掲載予定
- 適性診断は、貨物の運転適性診断(初任診断・適齢診断・特定診断)の受診が必要です。
- 運転適性診断は、2025年3月末までに貨物軽自動車運送事業経営届出を行った事業者は、2028年3月までに受診が必要です。2025年4月以降に貨物軽自動車運送事業経営届出を行った事業者は、猶予期間はありません。
「eナスバ」12月からスタート~運行管理者指導講習がeラーニングで受講可能に~(2024年10月1日・ナスバ(独立行政法人自動車事故対策機構))
運行管理者などを対象に行っている、運行管理者指導講習をナスバでは従来の方式に加え、新たに国土交通省よりeラーニング講習の認定を取得し、一般講習および基礎講習のeラーニング講習「eナスバ」を立ち上げました。
2024年11月1日より申込みを受付開始し、12月1日より開講いたします。
- 自宅や職場など、インターネット環境があればどこでも受講可能で、しかも受講期間内であれば繰り返し受講可能。
- 受講期間内であれば、好きな時間に受講可能です。
- 受講料は一般講習3,860円(税込み)、基礎講習9,560円(税込)※テキスト代・テキスト配送料込み。
- 講習会場への移動が不要なので、移動時間が節約できます。
- テキストは、受講申込みを行い、受講料を支払った後に配送します。
- 受講料はクレジットカード決済やペイジーによる事前決済。
- 領収書や修了証明書も「eナスバ」から入力することができます。
※通常の一般講習が3,200円(税込)・基礎講習が8,900円(税込)のため、少し割高ですが、手間や交通費などを考えると、とても魅力的な選択肢です。
2024年9月
「交通DX・GX による経営改善支援事業等」 及び「交通サービスインバウンド対応支援事業」等の2 次募集を実施します(2024年9月20日・国土交通省)
国土交通省では、交通事業者の経営改善に資するDXや訪日外国人旅行者の受入れ環境の整備に資する事業を実施する者に補助金を交付しています。このたび、日本版ライドシェア・公共ライドシェアの導入等を支援するために補助金の2次募集を実施します。
| 補助対象事業者 | 一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、レンタカー事業者、自家用有償旅客運送者(交通空白地有償運送を行う者に限る)等 |
|---|---|
| 公募期間 | 2024年9月27日(金)~12月27日(金)16時 予算が無くなり次第終了します。この場合、交付申請審査順に交付決定します。 |
| 補助対象 | 日本版ライドシェア・公共ライドシェアを導入するために必要なデジタル化に資する設備等 バス、タクシー事業の訪日外国人旅行者対応に必要な設備等 福祉タクシー等の公共交通のバリアフリー化に必要な設備等 |
自動車のヘッドライト「オートレベリング機能」2027年9月より全車義務化(2024年9月20日・国土交通省)
オートレベリング(自動式の前照灯照射方向調節装置)について、光源が2,000lm超の高輝度のすれ違い用前照灯を有する自動車は備えることとなっていたところ、国際的な合意に伴い、光源の輝度にかかわらず、レベリング装備を必要とする全ての自動車に備えることとしました(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、被牽引自動車等を除く)。
2024年9月20日公布、2024年9月22日施行。
| 乗車定員10人以下の新型車 | 2027年9月1日より適用 |
|---|---|
| 乗車定員10人以下の継続生産車 | 2030年9月1日より適用 |
| 車両総重量3.5t超の貨物車および乗車定員11人以上の新型車 | 2028年9月1日より適用 |
| 車両総重量3.5t超の貨物車および乗車定員11人以上の継続生産車 | 2031年9月1日より適用 |
自家用車活用事業(日本版ライドシェア)における大都市部以外の地域における供給車両数・時間帯の拡充について(2024年9月17日・国土交通省)
配車アプリが普及していない地域に、タクシー事業者から自家用車活用事業(日本版ライドシェア)の実施意向があった場合は「簡便な方法」として、金曜日・土曜日の16時台~翌5時台をタクシーが不足する曜日・時間帯とし、当該営業地域内のタクシー車両数の5%を不足車両数とみなしています。
これを超えて、日本版ライドシェアによる供給が必要な曜日・時間帯において具体的な申し出があった場合、管轄の地方運輸局などが必要と認めた場合は、日本版ライドシェアが稼働できる曜日や時間帯、使用可能車両数の拡大を可能としました。
- 曜日・時間帯の拡大
- タクシーが不足している曜日・時間帯が把握できる運行実績を収集し、提出が必要。
- また、その申し出があった場合には、その営業区域内のタクシー事業者にその旨を周知し、申し出を行ったタクシー事業者以外のタクシー事業者から運行実績の提出があった際は、その実績も斟酌する。
- 使用可能車両数の拡大
- 管轄の地方運輸局などが必要と認めた場合は、営業区域内のタクシー台数の10%まで使用可能車両数を引き上げることができる。
- タクシーが不足していることが把握できる運行実績を収集し、提出が必要。
- また、その申し出があった場合には、その営業区域内のタクシー事業者にその旨を周知し、申し出を行ったタクシー事業者以外のタクシー事業者から運行実績の提出があった際は、その実績も斟酌する。
自家用車活用事業(日本版ライドシェア)の制度改正(2024年9月10日)
自家用車活用事業(日本版ライドシェア)について、以下の制度改正を行いました。
- 災害対応時の自家用車活用事業の活用
- タクシーの営業区域外旅客運送制度を活用しても不足する場合には、地方公共団体や復旧・復興の移動ニーズを有するものから管轄の運輸局などに要望書が提出され、運輸局などが必要と判断した場合は、運輸局などが定めた期間内で自家用車活用事業(日本版ライドシェア)の活用。
- 配車アプリを使用しない自家用車活用事業の導入(電話申込み)
- 日本版ライドシェア利用の利用者からの同意、合理的なルートのおよび運賃・料金の同意を得る。
- 各種割増および割引を適用する。
- 各種料金は事前確定運賃とは区分して適用する。
- 運送途中で利用者の都合によってルートや目的地を変更する場合は、自家用ドライバーは営業所に連絡をし、変更地点を経由地として、新しい目的地までの距離を算出し、その総距離に応じて運賃を算出する。
- 利用者による対価の支払いは、現金でも可能。運行終了後、売上金をタクシー事業者に渡す。
- 配車依頼を受けたタクシー事業者は、利用者に対して乗車地点に到着する車両の詳細(自動車登録番号など)および到着までの所要時間を伝える。
- 貨客混載(繁忙期有償運送)の活用開始
- 日本版ライドシェアを実施する法人タクシー事業者は、一般貨物自動車運送事業の許可を取得し、さらに繁忙期有償運送の許可を得ることによって、自家用車活用事業の車両を貨物運送に使用できる。
- 協議運賃の取扱い開始(地域限定・事前確定運賃)
国土交通省「交通空白」解消本部、第2回目の会合を開催。交通空白解消へ官民連携の新組織を年内に設立(2024年9月4日)
国土交通省は4日、公共交通機関を利用するのが困難な交通空白地の解消に向け、官民連携の新組織を年内に設置すると発表しました。国や自治体や交通事業者、配車アプリなどのサービスを持つ企業が連携します。
10月より、車検の項目に「電子装置の検査(OBD検査)」が追加されます!(2024年9月4日・国土交通省)
近年、普及する自動ブレーキ等の先進安全技術は、交通事故の防止に大きな効果が期待される一方、正しく作動するためには定期的な検査が必要です。
国土交通省では、平成29年度より「電子装置の検査(OBD検査)」の導入について検討を重ね、令和元年の道路運送車両法改正等により関係法令を整備し、本年10月1日より、車検の検査項目として追加されます。これにより、先進安全技術の故障による不作動・誤作動を防止します。OBD検査は、令和3年10月(輸入車は令和4年10月)以降の新型車のみが義務の対象となります。
Uber Japan、日本初『ライドシェア×カーシェア』ライドシェアドライバー向けのカーシェアプログラムの提供開始 タイムズモビリティ、ロイヤルリムジンと協業発表(2024年9月3日・Uber Newsroom)
Uber Japan株式会社、タイムズモビリティ株式会社およびロイヤルリムジン株式会社が協業し、自家用車を所有していない方でもライドシェアドライバーになれる機会を増やせるように、タクシー会社のドライバーの採用活動をUberや支援します。この取り組みは、東京・有楽町にて2台から開始し、順次対象エリア内でカーシェア拠点を拡大していく予定です。これは、日本版ライドシェアにおける取り組みです。
2024年8月
自家用車活用事業(日本版ライドシェア)の制度改正(2024年8月2日)
自家用車活用事業(日本版ライドシェア)のイベント・酷暑時の増車が可能となるように、バージョンアップを実施しました。
2024年7月
国土交通省「交通空白」解消本部を立ち上げ(2024年7月17日)
全国各地で、タクシー、乗合タクシー、日本版ライドシェアや公共ライドシェア等を地域住民や来訪者が使えない「交通空白」の解消に向けて早急に対応していくため、国土交通省「交通空白」解消本部(本部長:国土交通大臣)を設置しました。
自治体・交通事業者とともに、「交通空白」の解消に向けた取り組みを進めていくとのことです。
また、第1回の会合の資料には、「公共ライドシェア」と「日本版ライドシェア」という単語が記載されています。
- 公共ライドシェア(自家用有償旅客運送のこと)
- 福祉有償運送
- 交通空白地有償運送
- 日本版ライドシェア(日本版ライドシェア)
- タクシー事業者の管理の下で、自家用車・一般ドライバーを活用した運送サービスの提供を可能とする自家用車活用事業(日本版ライドシェア)のこと
令和6年度 日本版MaaS推進・支援事業で11事業を選定(2024年7月16日)
国土交通省では、地域の課題解決に資するMaaSのモデル構築を図る「日本版MaaS推進・支援事業」について、他分野連携やサービスの広域化等の促進によりMaaSの更なる高度化を図る取組として、11事業を選定しました。
2024年6月
自家用車活用事業(日本版ライドシェア)の制度改正(2024年6月28日)
自家用車活用事業(日本版ライドシェア)の雨天時のライドシェア増車が可能となるように、バージョンアップを実施しました。
令和6年度 「共創・MaaS実証プロジェクト」(日本版MaaS推進・支援事業)の公募開始(2024年6月19日・国土交通省)
国土交通省では、公共交通の利便性向上や、環境対策や観光振興などの地域が抱える課題の解決に資する重要な手段として、MaaSの普及を推進しています。
他分野連携やサービスの広域化等を促進することで、MaaSの更なる高度化を図るため、日本版MaaS推進・支援事業の公募を開始します。この事業の公募・採択については、スマートシティ関連事業を実施する関係府省と一体で取り組みます。
郵便局、農協の活用本格化 過疎地向けライドシェア(2024年6月8日・共同通信)
政府は、過疎地の住民や観光客の移動手段確保に向けた輸送サービスの担い手として、郵便局や農協、観光地域づくり法人(DMO)といった地域組織の活用を本格化する方針を固めました。運送主体は、郵便局や農協などの他に観光協会、商工会、地域運営組織を想定しています。運転手は各組織の職員や地元住民が担います。
これは、交通空白地有償運送(公共ライドシェア)の取り組みです。
2024年4月
自家用有償旅客運送の運用改善について(2024年4月26日改正)
- ダイナミックプライシングの導入
- 運送の対価について、距離制・時間制・定額制のいずれかを選択した上で、需給の変動等に対応して、対価の額を変動させることも可能です。
- タクシー会社との共同運営の仕組み(共同輸送サービスの提供)の構築
- 事業者協力型自家用有償旅客運送を実施する場合には、近隣のタクシーの配車が困難な場合に自家用有償旅客運送自動車を配車するサービスを導入することが可能になります。
- 自家用有償旅客運送者が収受する金額について、自家用有償旅客運送に係る対価に地域の公共交通の確保維持に活用するための協力金を加え、当該地域のタクシー運賃と同額とすることが可能になります。協力金の使途及び管理者については、当該共同輸送サービスの提供について協議を行う地域公共交通会議において、協議を調えることが必要です。なお、その協力金の使途は、たとえばタクシー・自家用有償旅客運送に使用できる共通クーポンに係る費用、共同輸送サービスの提供に必要となる施設及び車両の高度化(遠隔点呼システム導入、キャッシュレス決済機器の導入、車両の購入費用など)、共同輸送サービスのドライバーの育成・人材募集、利用者拡大のためのマーケティング費用などに充てることが可能です。
- 地域公共交通会議の運営手法の見直し
- 地域公共交通会議で2ヶ月程度協議してもなお結論に至らない場合は、協議内容を踏まえ首長の責任により判断できることを通達上明記します。
- 運送の区域の設定の柔軟化
- 運送区域外への往復を可能とする必要性が高いことから、発地または着地のいずれかが運送区域内にあればよいことを通達上明記します。
精神障がい者の鉄道運賃割引、JR6社と大手私鉄16社すべてで順次導入へ
障害者の鉄道運賃の割り引き制度で、JR6社と大手私鉄9社は対象を拡大し、新たに精神障がい者を割引の対象にすると発表しました。
新たに制度を導入する事業者のうち、最も早いのが京成電鉄の乗車券の販売で今年6月からとしているほか、JR6社は来年4月からだということです。また、中小の私鉄でも複数の事業者が今後、新たに精神障がい者の割引制度を導入するということです。
- 介助者と同伴の場合
- 1種(障がいの等級が1級):普通券と定期券(小児の定期券を除く)など+介助者1人も半額
- 12歳未満の2種(2・3級):定期券のみ(小児の定期券を除く)+介助者1人も半額
- 1人で乗車する場合:1種・2種:片道の営業キロが100km超の場合に限り、普通券が半額
2024年3月
自家用車活用事業(日本版ライドシェア)の創設・方針発表(2024年3月29日)
国土交通省では、タクシー事業者の管理の下で地域の自家用車や一般ドライバーによって有償で運送サービスを提供することを可能とする制度(自家用車活用事業)の取り扱いについて通達を発出いたしました。
- 自家用車活用事業の進め方
- 自家用車活用事業(日本版ライドシェア)の許可申請について
- 自家用車活用事業における運行管理・車両整備管理について
ラストマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて(2024年3月29日・国土交通省)
近年の消費者ニーズの多様化や電子商取引の増加等を背景として、ラストワンマイル輸送を中心に、事業用自動車のみでは輸送力の確保が困難となっていることから、道路運送法第78条第3号に基づき、自家用自動車の有償運送の許可に係る取り扱いについて、弾力的な運用の規定を定めました。
この通達は、2025年1月1日以降に利用計画とするものから適用となります。2024年12月31日までは、「年末及び夏季等繁忙期におけるトラック輸送について(繁忙期有償運送)」通達により、許可申請が必要となります。
旅客・貨物の運行管理に関する講習の認定に関する実施要領の一部改正(2024年3月29日公布・国土交通省)
旅客・貨物の運行管理に関する講習の認定に関する実施要領の一部改正の告示(国土交通省告示)について通知が行われました。主な改正内容は以下の通りです。2024年3月29日公布・施行です。
これにより、運行管理者指導講習のオンライン講習が可能となりました。
- ICT 機器を使用したオンライン講習の普及を促す環境を整えるべく、講習の認定に関する実施要領(平成24年国土交通省告示第458号(旅客)・第459号(貨物))の所要の改正を行う。
- 講習のデジタル化を図るべく、運行管理者手帳による証明を必須とせず、電磁的記録による修了証明書の発行による証明も可能とする。
介護報酬改定、障害福祉サービス等の報酬改定
訪問介護(通院等乗降介助を含む)の報酬が、従来よりもすべて減算に変更となりました。
また、特別養護老人ホームに対して、厚生労働省は介護報酬改定で、透析が必要な高齢者の病院への送迎を評価する加算(特別通院送迎加算)を新設しました。この送迎は自家輸送(無償運送)扱いとなるため、旅客自動車運送事業や自家用自動車による有償運送の許可や登録は不要です。
これに伴い、厚生労働省老健局から「介護輸送に係る法的取扱いについて、介護予防・日常生活支援総合事業による高齢者の移動支援に係る交通施策との関係等について(2024年3月29日・厚生労働省老健局)」という事務連絡が出ました。訪問介護や障がい福祉サービスの移動支援等による送迎や、通所介護や通所リハビリ等の事業所による送迎の法的取扱いについて詳しく明記されています。ガソリン代等実費徴収の範囲内や、送迎加算の範囲内の送迎については自家輸送(無償運送)、ガソリン代等実費を超える金額を徴収する場合は、道路運送法上の許可や登録が必要です。
通所介護や障がい福祉サービスの共同送迎を新たに認めるように(2024年3月15日)
厚生労働省は新年度の介護報酬改定で、デイサービスの複数の事業所が利用者を共同で送迎することを認めました。今月、新たに公表した改定のQ&Aでその解釈を明示しました。
- A事業所の利用者をB事業所の職員が送迎する場合、A事業所がその職員と雇用契約を無杉、費用負担や責任の所在といった条件を事業所間で話し合って決めていれば、利用者を同乗させることは差し支えない。
- 複数の事業所で送迎を第三者に共同委託する場合、同様に事業所間で合議・決定することを前提に、利用者を同乗させることは差し支えない。
- 対象サービスは通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・通所リハビリテーション・療養通所介護など。障害福祉サービスの利用者の同乗も可能。
- 送迎範囲は利用者の利便性を損なうことのない範囲、各事業所の通常の事業実施地域の範囲とする。
道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関する新ガイドライン発表(2024年3月1日)
- 道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて(2024年3月1日国自旅第359号)
- イラスト版
介護保険制度上の訪問介護(通院等乗降介助)、障がい福祉サービスの居宅介護(通院等乗降介助)・同行援護・行動援護・重度訪問介護・移動支援(市町村の地域生活支援事業)の送迎が、ガソリン代等の実費徴収の範囲内であれば、旅客自動車運送事業や自家用自動車による有償運送の許可や登録は不要となるよう変更となりました(ガソリン代等実費を超える金額を徴収する場合は、道路運送法上の許可や登録が必要です)。
2023年
2023年12月
交通空白地有償運送の「株式会社が保有する自家用車の活用」及び「観光地において宿泊施設が保有する自家用車の活用」について(2023年12月28日・国土交通省)
輸送資源が足りないことが多い、交通空白地有償運送の実施地域において、実施主体からの受託により株式会社が参画することは、サービスを充実させる観点から効果的であると考えられ、以下の各種施策が取りまとめられた。
- 実施主体からの受託により株式会社が参画するケース
- たとえば、配送行為を行う株式会社が配送ルートの途中で旅客を運送するなど、自治体等に協力して実施する場合
- 観光地において宿泊施設が共同で車両を活用するケース
- 複数の宿泊施設で使用していない時間帯の車両を持ち寄り、実施主体である自治体や観光協会などにドライバーも含め提供し、ホテル間や観光スポットへの宿泊者及び観光客の運送や、病院、スーパー等への地域住民等を運送する場合
などにより、移動の足不足に対するニーズに自家用車の活用が期待できます。具体的な手続き方法は以下の通りとなります。
- 自家用有償旅客運送者(申請者)に対しての宿泊施設など株式会社からの持ち込み自動車の取り扱いについては、「交通空白地有償運送の登録に関する処理方針について」に基づき処理します。
- 持ち込み車両については、自家用有償旅客運送を実施する間は、実施主体がその自動車の使用権原を有していることが必要です。その使用権原を証する書類等は、持ち込み自動車の自動車検査証および、自動車の使用者と申請者の間で結ばれた契約書または使用承諾書となります。この契約書または使用承諾書は、交通空白地有償運送を実施する間、使用権原および運送に伴う責任が申請者にあることを定めたものであるものとします。
- 自家用有償旅客運送者に協力した株式会社に対する委託費については、道路運送法第79条の8の規定(運送の対価は実費の範囲内とする規定)にかかわらず、株式会社の利潤(利益)も含めた支払いが可能です。
詳細については、こちらの事務連絡をお読みください。
地域公共交通会議および運営協議会に関する国土交通省としての考え方について(2023年12月28日改正・施行)
- 自家用有償旅客運送の有効期間の更新登録時の協議方法の簡素化
- 地域公共交通会議等において、自家用有償旅客運送の更新登録を行う際は、意見公募形式によって地域公共交通会議等の構成員に対して周知し、一定期間異議がない場合には、当該更新にかかわる協議が調ったものとみなすように変更。
- 交通空白地に該当する目安を提示
- 交通空白地有償運送の必要性が認められる場合とは、過疎地域や交通が著しく不便な地域において、バス・タクシー等の交通事業者による輸送サービスの供給量が不十分であるなどの事情により、旅客運送の確保が困難となっている場合などが想定され、交通空白地有償運送の必要性については、地域の実情に応じて地域公共交通会議等において適切に判断される必要があります。
- 半径1km以内にバスの停留所および鉄軌道駅が存在しない地域で、タクシーが恒常的に30分以内に配車されない地域や、もしくはその地域におけるバス・タクシー・鉄軌道事業者の営業時間外の場合は、少なくとも交通空白地(交通サービスが限られる時間帯が生じる地域を含む)に該当することを前提に、交通空白地有償運送の必要性を地域公共交通会議等において判断することが望ましい。
自家用有償旅客運送者が収受する対価の取扱いについて(2023年12月28日改正・施行)
- 対価の設定目安をタクシー運賃の約8割の水準まで引き上げ
- 従来はタクシー運賃の概ね2分の1の範囲内となっていましたが、これをタクシー運賃の約8割まで引き上げました。ただし、地域公共交通会議等において調った協議結果に基づき、約8割を超える運送の対価を設定することも可能です。
- 対価の目安の考え方を新たに提示
- 経常費用として人件費、燃料油脂費、車両修繕費(タイヤ費用を含む)、車両償却費(リース費を含む)、その他諸経費(諸税(自動車税、自動車重量税等)、保険料等を含みます。
- 当該地域の直近のタクシー距離制初乗り上限運賃を算出する際に使用した各経常費用項目の合計をもとに構成比を算出、構成比割り付けし、合算。
- 地方運輸局および沖縄総合事務局にて、インターネットその他の適切な方法により対価の目安を公表
いずれも対価の目安であるため、地域公共交通会議等において目安に拘束されるものではありません。
安全運転管理者選任事業所および、自家用有償旅客運送事業者の特定事務所のアルコール検知器を用いたアルコールチェック義務化(2023年12月1日施行)
2023年11月
道路運送法施行規則改正(手続き簡素化・運送事業者との連携拡大)(2023年11月2日改正・施行)
- 事業者協力型自家用有償旅客運送に配車サービスの提供を追加
- 更新登録の手続き簡素化(添付書類の省略化)
介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送・福祉輸送事業限定)の許可要件が緩和されました(2023年11月1日・国土交通省)
- 営業所、車庫、休憩仮眠施設の使用権原が3年以上だったものが、1年以上で良くなりました。
- 車庫は、従来駐車した際に前後左右それぞれ50cmの隙間を確保できる区画があるのが必要でしたが、「確実に収容できる」区画があれば良くなりました。
2023年10月
道路運送法施行規則改正(運営協議会関係)(2023年9月22日改正・2023年10月1日施行)
協議の場を運営しやすくするため、「運営協議会」を「地域公共交通会議」へ統合。
ただし、今回の改正においては必ずしも実質的な統合を要するものではなく、既存の運営協議会をそのまま存続させることも可能。
2023年8月
道路運送法施行規則改正(運転者証の車内掲示削除等)(2023年9月22日改正・2023年10月1日施行)
運転者証の作成・車内掲示義務を廃止し、自家用有償旅客運送者の名称・自動車登録番号を車内へ掲示するように変更。
2023年7月
車検ステッカーの貼り付け位置が変更となりました(2023年7月3日)
フロントガラスに貼る車検ステッカーの位置が変わります。
公道を走るうえで、すべての車は車検に合格している必要がありますが、その有効期間を示しているのが検査標章(通称・車検ステッカー)です。車検ステッカーは以前からフロントガラスの上部に貼られていましたが、2023年7月3日から貼り付け位置が変わることになりました。
具体的には「前方から見やすい位置(従来は、主に車両中央部(ルームミラーの下)に貼られていました)」から「前方かつ運転者席から見やすい位置(運転者席上部で、車両中心から可能な限り遠い位置)」に変更となります。
既存の車検シールは引き続き使用することができます。有効期限が到来し、車検を受けた後に新しい位置に車検シールを貼り付けます。
電動キックボードなど(特定小型原動機付自転車)の施行(2023年7月1日施行)
新たな交通手段として期待されている電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車。
2023年7月1日から法律が変わり、電動キックボードなど、特定小型原動機付自転車の新ルールがスタートしました。これにより、特定小型原動機付自転車では原則として運転免許が不要となり、ヘルメットの着用が努力義務になるなど、さらに利用しやすくなりました。
2023年5月
貨客混載制度の実施区域の見直し(2023年5月30日)
地域におけるニーズを踏まえ、貸切バス事業者やタクシー事業者がトラック事業の許可を 取得した上で、過疎地域以外においてもバス・タクシー事業に用いる車両で貨物の運送を行うことができることとする等の措置を講じました。
具体的には、貸切バス事業者及びタクシー事業者によるトラック事業の許可の取扱いについて、地域の関係者による協議が調ったことを条件として、過疎地域以外においてもバス・タクシー事業に用いる車両で貨物の運送を行うことができることとします。
また、トラック事業者による乗合バス事業、貸切バス事業及びタクシー事業の許可の取扱いについても、地域の関係者による協議が調ったことを条件として、過疎地域以外においてもトラック事業に用いる車両で旅客の運送を行うことができることとします。
2023年2月
高速道路・有料道路の障がい者割引制度の拡大、事前登録した車以外でも障害者割引が利用可能に。オンライン申請も導入(2023年2月10日発表・2023年3月27日より適用)
NEXCO3社、首都高、阪神高速、JB本四高速は、有料道路での障害者割引制度を見直し、3月27日から適用します。
これまでは事前登録された自家用車に限り割引を適用していたが、知人の車やレンタカーを利用する場合、介護が必要な重度の障害者がタクシーや福祉有償運送を利用する場合など、事前登録がない自動車でも割引の適用対象となります。利用には事前申請が必要で、これとあわせオンライン申請を導入するとのことです。
なお、事前登録された自家用車以外の車で通行する場合は、ETCカードによるノンストップ通行はできません。
- 身体障がい者自らが運転をし、有料道路を使用する場合
- 知人の車やレンタカー、社会福祉協議会で借りた車などが対象となります。
- 重度の身体障がい者または知的障がい者が同乗し、介護者が運転する場合
- タクシー(介護タクシーを含む)、福祉有償運送
2023年1月
普通車・小型車・軽自動車の電子車検証の交付が始まりました(2023年1月4日・国土交通省)
2023年1月4日、普通車・小型車・軽自動車の電子車検証の交付が始まりました。電子車検証の券面には、有効期間や使用者住所、所有者情報が記載されないため、ユーザーや関係事業者は車検証閲覧アプリを利用して、電子車検証情報を確認することができます。
既存の車検証は、引き続き使用することができます。有効期限が到来し、車検を受けた後に電子車検証に切り替わります。
2022年
2022年10月
貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について(2022年10月24日)
貨物軽自動車運送事業の経営の届出の受理に当たっては、軽貨物事業経営届出等取扱通達に基づき、最大積載量の記載のある車両に限って認めてきたところですが、今般、「規制改革実施計画」を踏まえ、軽乗用車についても、貨物軽自動車運送事業の用に供することを可能とし、届出の受理の取扱いについて規定しました。
道路交通法および、道路運送法施行規則の改正(安全運転管理者および、自家用有償旅客運送の特定事務所の運行管理の責任者の制度改正)(2022年10月1日施行)
- 道路交通法の改正により、道路運送法第79条に規定する自家用有償旅客運送(福祉有償運送・交通空白地有償運送)の事業者は、安全運転管理者の選任義務対象から外れることになりました(解任して構いません)。
- 代わりに、一定台数以上の有償運送の自動車を運用する事業所(特定事務所)の自家用有償旅客運送者は、資格等を有する運行管理の責任者を選任しなければなりません。また、その特定事務所の運行管理の責任者に対し、新たに運行管理者一般講習(旅客)を2年ごとに受講する義務が課せられることになりました。
2022年5月
新運転免許制度が施行!二種免許の取得条件緩和、75歳以上の運転技能検査、サポカー限定免許(2022年5月13日施行)
運転免許制度が、以下の通りに変更となりました。
- 高齢運転者対策
- 一定の違反歴のある75歳以上の高齢者に対し、運転技能検査を義務化
- 既存の高齢者講習・認知機能検査の内容変更および、手数料の改定
- サポカー(安全運転サポート車)限定免許の新設
- 特別な教習を修了した者について、第二種運転免許などの受験資格の見直し(取得条件緩和)
- 若年運転者期間に、基準に該当する違反を行った場合は、若年運転者講習(9時間)の義務付け
2022年4月
安全運転管理者選任事業所の業務拡充(アルコールチェック義務化)(2022年4月1日施行)
一定台数以上の自動車を使用する自動車の使用者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として安全運転管理者の選任を行わなければなりません。
業務使用の自家用自動車における飲酒運転防止対策を強化することを目的として、令和3年の道路交通法施行規則の改正により、① 安全運転管理者に対し、目視等により運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと及びその内容を記録して1年間保存することを義務付ける規定(令和4年4月1日から施行)② 安全運転管理者に対し、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと並びにその内容を記録して1年間保存すること及びアルコール検知器を常時有効に保持することを義務付ける規定が設けられました。
2021年
2021年3月
介護報酬改定、障害福祉サービス等の報酬改定
今回の介護報酬改定・障害福祉サービス等の報酬改定により、訪問介護・居宅介護の通院等乗降介助実施時に、複数の目的地への立ち寄りが可能となるように変更(改善)されました。
また、重度訪問介護で移動介護緊急時支援加算という報酬が追加されるように変更(改善)されました。常時介護が必要な方を送迎する際に、自動車を駐停車などを行って適時適切な支援(たとえば、喀痰吸引などの医療的ケアや体位調整等の支援など)を行った際に加算されるものです。
2020年
2020年11月
道路運送法施行規則改正および通達の一部改正(自家用有償旅客運送関係)(2023年5月可決成立・2023年11月27日施行)
- 自家用有償旅客運送が、福祉有償運送と交通空白地有償運送の2種類へ変更(市町村運営有償運送を福祉有償運送・交通空白地有償運送へ統合)
- 福祉有償運送の利用対象者がイロハニから、イロハニホヘトへ変更となりました。
- 福祉有償運送の旅客の範囲の変更・拡大・縮小において、変更登録時に運営協議会での協議が必要に変更になりました。
- 交通空白地有償運送の利用対象者が、新たに観光旅客も含まれるように変更となりました。