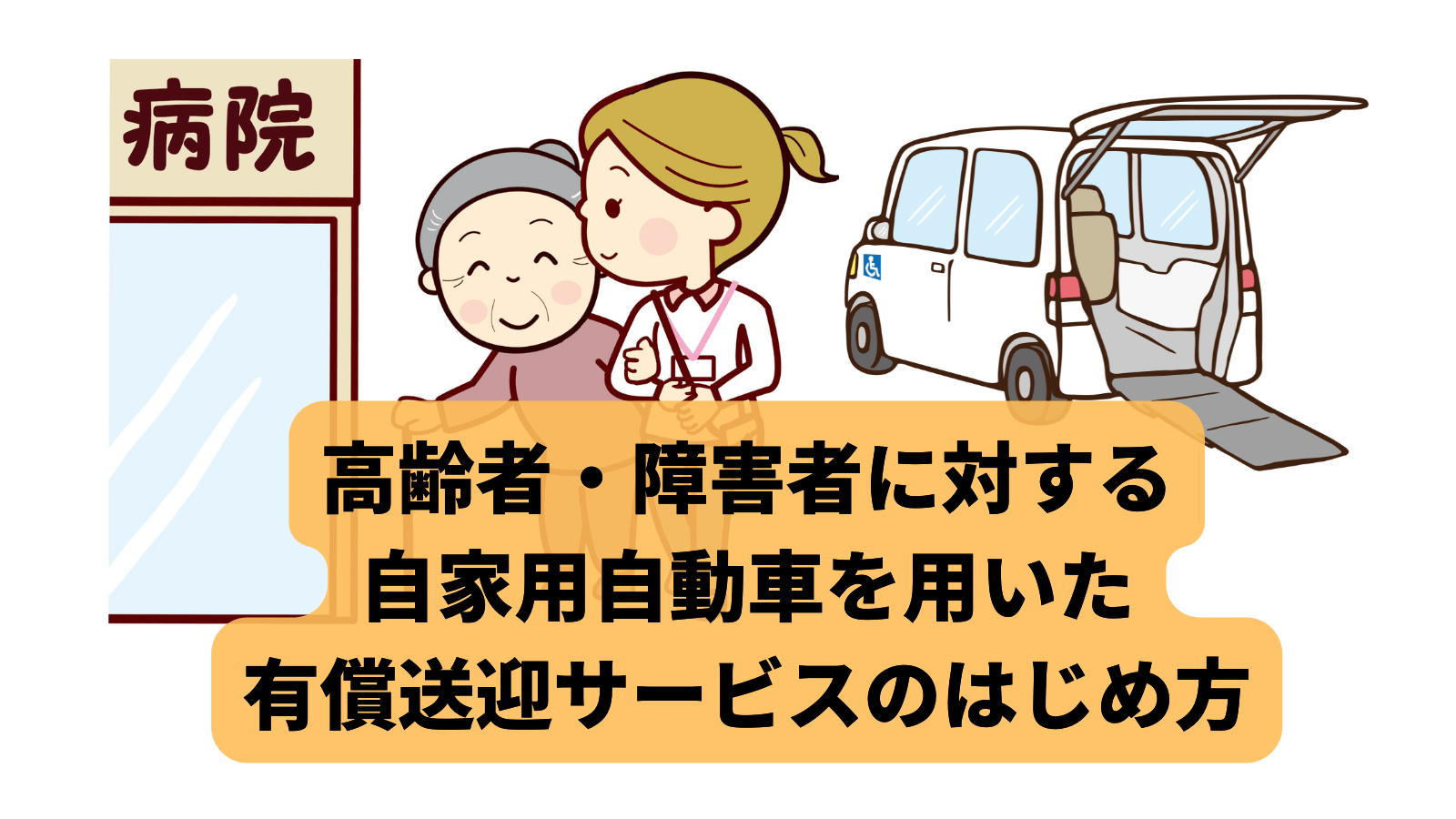日本国内では、条件付きではあるものの、自家用自動車を用いて有償でタクシーのような送迎業務を行うことができるようになっています。
自家用自動車とは、白色もしくは黄色のナンバープレートの自動車(軽自動車・普通自動車等)を指します。そして、自家用自動車を用いて有償で送迎輸送(これを、有償運送といいます)を行う場合には、基本的に2種免許の取得は不要です。これだけ聞くと、とても魅力的なように感じますね。現状、2種免許を取得していない方が、新たに免許を取得するとなると時間的・費用面でのコスト等が必ず発生するからです。
これらの、自家用自動車を用いた有償運送(主に人を送迎輸送するもの)を、以下に分類してみました。
| 福祉有償運送(公共ライドシェア) | 実施事業者:市町村(自治体)および、NPO法人・社会福祉法人等の非営利法人・団体 利用対象者:介護を必要とする高齢者・障害者など ※他の有償運送とは異なり、利用対象者の名簿管理(会員管理)が必要。利用者は、サービスを利用するためには会員登録が必要。 |
| 交通空白地有償運送(公共ライドシェア) | 実施事業者:市町村(自治体)および、NPO法人・社会福祉法人等の非営利法人・団体 利用対象者:地域に在住する住民・観光旅客など、その地域の来訪者(健常者を含む) |
| 訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可) | 実施事業者:タクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業、介護タクシー(福祉輸送事業限定)を含む)または特定旅客自動車運送事業を行う訪問介護・居宅介護事業者(営利法人もしくは非営利法人) 利用対象者:上記の訪問介護・居宅介護サービスの利用者(高齢者・障害者)※ ※利用可能な範囲は、訪問介護(介護保険)・居宅介護サービス(居宅介護・行動援護・同行援護・重度訪問介護・移動支援)の範囲内に限られる。いわゆる保険外サービスとしての提供は不可。 |
| 自家用車活用事業(日本版ライドシェア) | 法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送 実施事業者:法人タクシー事業者(一般乗用旅客自動車運送事業、介護タクシー(福祉輸送事業限定)を除く) 利用対象者:配車アプリを使用した利用者(健常者を含む) |
| 過疎地域の乗合バス事業者による自家用自動車の有償運送 | 過疎地域における一般乗合旅客自動車運送事業(区域運行)の輸送力補完のための自家用自動車の有償運送 実施事業者:過疎地域における乗合バス事業者(一般乗合旅客自動車運送事業) 利用対象者:健常者を含む |
| 通学通園に係る自家用自動車の有償運送 | 実施事業者:幼稚園、保育所、小学校、中学校、盲学校、聾学校又は養護学校 利用対象者:上記学校等に通う幼児、児童又は生徒 |
| 災害のため緊急を要するとき | |
| 上記に該当しない場合 | 現状では、自家用自動車で有償運送を行う選択肢なし。 個人事業主(法人を含む)の場合は、有償運送に該当しない範囲で許可又は登録不要の運送(共助型ライドシェア)を行うか、もしくは運送中も反対給付(運転手の運送中の人件費を含むもの)を請求する場合、介護タクシー(福祉輸送事業限定)の許可申請を行うことで介助が必要な高齢者・障がい者に対し、有償での送迎輸送が可能。事業用自動車という扱いになり、二種免許取得が必要。 |
上記いずれかの中で、介護・障害福祉サービスを提供している事業者が、自家用自動車を用いて有償運送を行う場合には、現実的には以下の選択肢となります。
- 福祉有償運送(79条登録)
- 訪問介護員等による有償運送(78条許可)
NPO法人・社会福祉法人等の非営利法人・団体の場合には福祉有償運送もしくは訪問介護員等による有償運送、営利法人(株式会社・有限会社・合同会社・合資会社等)の場合には訪問介護員等による有償運送といった選択肢になります。
よく「自家用有償旅客運送」という言葉が出てきますが、この自家用有償旅客運送というキーワードに対応するものは、正しくは上記のうち福祉有償運送・交通空白地有償運送の2種類だけが当てはまります。
時々、他の有償運送についても「自家用有償旅客運送」と表記しているホームページ等がありますが、これは正しい表現ではありません。
他の類型も含めて、国土交通省が「高齢者の移動手段確保のための制度と地域の取組モデルについて」整理・解説したパンフレットを公表しました。よろしければご覧ください(2024年に制度改正が行われた部分については、併せて当社ブログ記事などをご参照ください)。
有償運送の許可や登録が不要な場合(共助型ライドシェア)
主に以下の場合には、有償運送の許可や登録が不要とされています。
許可又は登録を要しない運送の新ガイドライン
本内容については、令和6年3月1日に「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて」という新ガイドラインが発出されました。下記以外の内容などについては、本ガイドラインを直接ご確認ください。
今回(令和6年3月1日)の改定のポイントは、以下の通りです。
無償運送の新しいガイドラインの基本的な考え方
これまで無償運送について、いくつもの通達が累次に出てきました。
その時々で国土交通省へ様々な質問が来て、それに対する通達としての回答を示してきたわけでありますが、これまでの複数の通達に関する内容をもう一度整理し、現在の状況を踏まえ、必要と考えられる内容も含めて取りまとめを行いました。
その取りまとめには、2023年にタクシー・バス会社、福祉輸送の方々、NPOの代表者等の複数の関係者と何度かにわたって勉強会を行い、議論を行った上で作成しました。
- 輸送というのは安全かつ継続性が第一なので、以下の順番を押さえます。
- バス・デマンド交通・タクシーなどの公共交通機関の活用を第一に考える。
- 公共交通機関による運送サービスが十分に確保できない場合には、道路運送法の定める自家用有償旅客運送制度を組み合わせて移動手段を確保する。
- それでも提供できない部分について、無償運送(地域での互助活動・ボランティア活動による運送・自家使用の自動車による運送等)も考えていく。
- 有償運送は道路運送法で規制をかけているが、無償運送は本来的には一定の考え方やルールを設けた範囲内において自由にできる・各自がやって良い(何かの具体例に当てはまらないと無償運送として認められない、という考え方ではない)ものである。
- したがって、「無償運送は、許可・登録を得ずに安心してやってください」ということを示すために、類型を整理して、ガイドラインとして示しました。
無償運送と有償運送との線引き
利用者から運送の反対給付として金銭を収受する場合を有償運送とし、反対給付として金銭を収受しない(ガソリン代等実費に収まる範囲)を無償運送(道路運送法における許可又は登録を要しない運送)としました。
有償運送は道路運送法で規制をかけていますが、無償運送は道路運送法による規制がなく、自由に行うことができます。また、無償運送なので、運送を行える範囲に制限はありません。
以下の行為は無償運送として行うことができます。有償運送ではないので、許可または登録は不要です。
- 任意の謝礼の支払い
- 利用者からの「ガソリン代等実費」の支払い
- 利用者以外から収受するもの(補助金や寄付金等)は反対給付としてみなされず、金銭を受け取ることができる
「ガソリン代等実費」の定義
利用者から支払いを受け取ることができる「ガソリン代等実費」の定義は以下の通りです。
- 反対給付として該当しない範囲「ガソリン代等実費」とは、運送(運送中や、運送前後の回送に必要な経費を含む)に必要なガソリン代・有料道路代・駐車料金のほかに、新たな実費対象として保険料・車両借料(レンタカー代)が加わります。
- ガソリン代の算出は、一般的には直近のガソリン価格等を利用して「走行距離÷燃費(km/l)×1lあたりのガソリン価格(円/l)で計算しますが、運送が頻繁な場合には一定期間「1kmあたり◯円」と定めて概算することも、簡易な方法として容認されます。
- 上記のガソリン代等実費を超えて、利用者からその他の費用(運転者に対する人件費等)が支払われた場合は反対給付とみなします。
- なお、上記の保険料とは「ボランティア団体等による1回あたり、または1日あたりの無償運送行為を対象に提供されている保険(該当保険が年間契約の場合を含む)」または「レンタカーの借り受けに伴って加入する一時的な保険(免責補償制度(CDW)および休業補償(NOC)」を指し、当該車両にもともと掛けられている自賠責保険や任意保険は対象外です。
- 重要なポイントは、これらが「その送迎が行われなかった場合には、発生しなかったことが明らかな費用」であることです。その送迎を行うことで発生したことが明らかな費用であれば、その送迎の利用者から金銭を受け取ることが可能になります。
- したがって、たとえば介護施設や幼稚園、自治会等が使用する車両が「主として送迎を行う利用者のためだけに購入・維持している場合(送迎専用車両の場合)」については、実費の範囲に車両償却費・車検料・保険料(当該車両に元々かけられている自賠責保険・任意保険)等の車両維持費)を含めても問題ありません。
- 一方で、たとえばボランティアや職員等が所有するマイカーを使用して送迎を行う場合には、送迎専用車両とは言い難いので、上記に記載した車両償却費・車検料・保険料(当該車両に元々かけられている自賠責保険・任意保険)等の車両維持費)を利用者から受け取って良い「ガソリン代等実費」に含めることはできません。
利用者から受け取っている金銭がまったくない場合
対価・報酬を得ずに送迎を行う場合(他の名目での報酬もまったく得ていない場合)は無償運送とみなします。
「任意の謝礼」とは
運送の提供者が金銭の支払いを求めず、利用者から「謝礼」として金銭等が支払われた場合は、社会通念上常識的な範囲での謝礼については、無償運送とします。
ただし、以下の場合には謝礼とは認められません。
- 運送を提供する者が運賃表を定めて、それに従って利用者が金銭を支払う場合。
- 口頭・ジェスチャー等により利用者に強く謝礼の支払いを促す等、謝礼の名を借りて実質的には運賃を求める場合。なお、この場合は「ガソリン代等実費」の支払いを求めることは可能です。
- ウェブサイト等により無償運送サービスを仲介・紹介するサービスで、謝礼を支払わないとサービスが提供されなかったり、謝礼の有無や金額の違いで差別的取り扱いを行う場合は、任意の謝礼とはみなされません。
施設等の送迎(デイサービスや通いの場、短期入所生活介護、その他の施設)
デイサービスや通いの場などの送迎を行う場合の留意点は以下の通りです。
- 目的地であるデイサービスや通いの場などの運営団体が、その施設等への送迎を一体的に行う場合、デイサービスや通いの場などの利用料を利用者から受け取ることは問題ありません。
- また、送迎の利用の有無によって「ガソリン代等実費」の範囲で利用料に差を設けても問題ありません。
- また、利用者からの依頼や要望に応じて、送迎途中で商店等に立ち寄っても問題ありません。
介護報酬上の加算(もしくは減算)というのは、たとえば障害福祉サービス事業者(具体例として、児童発達支援・放課後等デイサービス・就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・生活介護・日中一時支援(地域生活支援事業)など)等が行う送迎輸送で、市町村が従来の送迎加算の範囲内の額(利用者負担分を含む)を給付する場合や、介護保険上の通所介護(デイサービス)・通所リハビリ施設等の送迎減算、特別養護老人ホームの透析の通院送迎を行った場合の特別通院送迎加算などがあります。
訪問介護や居宅介護等における移動支援サービスの送迎
従来では「訪問介護サービス等に連続して移送を行う場合は道路運送法上の許可又は登録を求める」こととし、これらを受けずに運送を行う訪問介護(居宅介護等の障がい福祉サービスも同様)事業所については介護報酬の対象としない」と強く書かれていましたが、今回の無償運送のガイドライン改定で、乗降介助が介護報酬の対象となっている場合でも、運送は介護報酬の対象外となる場合には、運送中に「ガソリン代等実費」を受け取って無償運送を行うことは可能となっています。
- 反対給付を受け取る場合には、有償運送の許可又は登録が必要です。
- 介護保険法に基づく訪問介護や、障害者総合支援法に基づく居宅介護、行動援護、同行援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援および、地域生活支援事業の移動支援で運送を行う場合においても上記と同様です。
- 介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスB・Dおよび、一般介護予防事業の一環として行う運送において、「提供するサービスに人の運送が付随して行われるもの」であり、運送に特定した反対給付がない限り、有償運送には該当せず、許可や登録は不要です。なお、委託を受けて通所サービス事業所等への送迎を実施する場合は、上記「施設等の送迎」の項目の取り扱いと同様。
- 地域支援事業交付金等から補助されるガソリン代等の実費ならびに、ボランティアに対するボランティアポイントおよびボランティア奨励金は運送の反対給付とはみなされないため、有償運送には該当せず、許可や登録は不要です。
生活支援サービスなどとの一体的な運送
ここでの「生活支援サービスなどとの一体的な運送」は、以下の2つのタイプがあります。
- ゴミ出しや庭の草取りなど、様々な生活支援サービスを提供するボランティア団体などにおいて、そのサービスの1つとして送迎が位置づけられていて、かつ他の生活支援サービスと一律の料金体系である場合。
- 一律の料金体系とは、たとえば1回あたり◯◯円、1時間あたり◯◯円といったものを指します。
- たとえば提供する生活支援サービスが「病院内や買い物施設内などにおける付き添い支援」や、子どもの送り届けが含まれる「子どもの見守り支援」のみであるボランティア団体などにおいて、送迎があくまでそれに付随して行われるものである場合。
- この場合は「病院内や買い物施設内などの付き添い支援」や「子どもの見守り支援」が有料であったとしても、送迎中に反対給付を受け取らなければ無償運送となります。
- これらの2つのタイプにおいて、「ガソリン代等実費」を追加で受け取ることも可能です。
ただし、どちらのタイプでも実態として送迎のみを行っている場合はタクシーと同じで有償運送とみなされ、道路運送法の許可または登録が必要になります。
また、子どもの塾・習い事・部活動等への無償送迎を、地域のボランティア・互助活動として組織的に行うことは差し支えないが、地域のタクシー事業者の中には「子育てを応援するタクシー」を実施している事業者もおり、こうしたサービスの活用促進にも留意されたい。
利用者以外から収受するもの(補助金や寄付金等)を受け取る場合(第三者からの給付)
運送主体が「利用者以外から収受するもの(補助金や寄付金等)」については、原則として「運送サービスの提供に対する反対給付」とはみなされず、無償運送と取り扱います。
- 国や地方公共団体からの団体の運営に要する費用の補助金や、第三者からの寄付金や協賛金についても、個々の運送行為と結びつかないものであれば、団体への給付金とみなし、団体職員や運転者などの人件費に充てる場合でも道路運送法の許可又は登録は不要で、無償運送と取り扱います。
- 運送主体が運送サービスのみを提供する団体等であったとしても問題ありません。
- 訪問介護の介護報酬(乗降介助)などについても、運送は介護報酬の対象外であるため、この考え方と同様です。
- 「ガソリン代等実費」に該当する費用が国や地方公共団体から補助されている場合は、補助金を受け取っている費用と重複した費用を利用者から「ガソリン代等実費」の範囲でも受け取ることは不適切です。
- 運送サービスの利用者に対し、国や地方公共団体が運送利用券を直接または間接的に給付する場合は有償運送とみなされ、道路運送法上の許可又は登録が必要となります。
- 国や地方公共団体がボランティア団体等に運送を委託する(運送主体が国や地方公共団体になる)場合は、この「第三者からの給付」には該当しません。
自治会等の地縁団体等が、会費の一部を送迎経費に使用した場合
社会福祉協議会、自治会・町内会・青年会、まちづくり協議会、マンション管理組合、老人クラブ等の地縁団体の活動として、会の運営経費全般に充てることを目的として受け取った会費で、その一部を送迎に係る経費に使用したとしても無償運送と取り扱います。
- 会費で車両を調達したり、会費から運転者の報酬を支払うことも可能です。
- また、運送サービスの有無によって「ガソリン代等実費」の範囲で会費に差をつけることも可能です。
- ただし、実質的に運送サービスのみを提供する団体等であるとみなされる場合には有償運送とみなされ、道路運送法の許可または登録が必要になります。
- ただし、もしも運送サービスのみを提供する団体等であっても、会費の徴収が「ガソリン代等実費」のみの範囲であれば、無償運送と取り扱います。この場合は反対給付として、運転者に対する人件費等を受け取ることはできません。
宿泊施設(ホテル・旅館等)の利用者を対象とする運送
宿泊施設(ホテル・旅館等)が、駅や空港、港等と宿泊施設間の無償送迎を行う場合、
- 送迎の利用の有無によって「ガソリン代等実費」の範囲で利用料に差を設けても問題ありません。
- 要望に応じて、送迎途中で商店等に立ち寄ることも可能。
- 送迎が長距離に及ぶ場合も、利用者対象のサービスとして社会通念上妥当な場合は許可や登録は不要。
- ホテル・旅館・農家民泊等が近隣施設や観光スポットへの運送(スキー旅館からゲレンデ、旅館から海水浴場、宿泊施設からイベント会場等)を無償で行うことも可能。
ツアー等のサービス提供事業者がツアー参加者を対象に行う、サービスに付随した運送
ツアー等のサービス提供事業者がツアー参加者を対象に行う、サービスに付随した無償送迎を行う場合、
- ダイビング・シュノーケリング等のマリンスポーツやスノーシューツアー等の事業者が、ツアー利用者を近隣の駅やバス停、宿泊施設等からツアー実施場所まで利用者を対象に無料サービスで行う運送は、社会通念上常識的な範囲のものは、許可や登録は不要。
- サイクリング・ツアー等で、ツアー参加者の突発的な体調不良・天候不良等により、ツアー参加者を伴走車に乗せる場合、運送に特定した反対給付がない場合は、許可や登録は不要。
- ただし、ツアーと称していても、提供されるサービスの実態が単に目的地のみへの運送である場合は、タクシーと同じで有償運送とみなされ、道路運送法の許可または登録が必要になります。
通訳案内士等による観光ガイド事業との一体運送
国や地方公共団体および、公益社団法人日本観光振興協会ならびに公的機関が認定・付与する資格(通訳案内士等)を有する観光ガイドが、ガイドのために人を運送する場合で、運送に特定した反対給付がない場合には、無償運送となり、「ガソリン代等実費」を受け取ることも可能です。
ただし、観光ガイドと称していても、提供されるサービスが当該地域に関する専門的な知識や高度な語学力等に基づくガイドの提供ではなく、単に目的地までの運送サービスのみである場合には有償運送とみなされ、道路運送法の許可または登録が必要になります。
その他有料の施設利用、学校・幼稚園等に付随する送迎サービスの場合
たとえば有料の施設利用や宿泊施設・幼稚園等に付随する送迎(運送)サービスについて、送迎利用の有無にかかわらず利用料に差異がない場合や、「ガソリン代等実費」の費用を別途徴収する場合については許可や登録は不要です。
また、幼稚園等において、「通学通園に係る自家用自動車の有償運送許可」を得た場合には、利用者から運行にかかる燃料費および運行に係る人件費にかかわる実費相当を徴収することが可能になります。
運転役務の提供について報酬が支払われた場合
他人の車両の運転を委託されて送迎を行う場合(自動車を用意せず、運転役務のみを提供する場合)は、運転役務の提供者に対して報酬が支払われたとしても有償運送には該当せず、許可や登録は不要です。
- ただし、運送の態様や対象の旅客の範囲によっては、自動車運転代行業・人材派遣業等とみなされる場合があるので、それぞれの関係法令が提供されることに留意が必要。
- 具体例として、「利用者の所有する車両を使用して送迎を行う場合(利用者自身が借りたレンタカーを含む)」「企業所有の車両を使用し従業員送迎を行う場合で、運転業務を外部に委託する場合」などが有償運送には該当せず、許可や登録は不要です。
- 車両提供者が、運転役務提供者に運転をさせて、第三者の利用者を運送する場合
- 車両提供者が利用者から「ガソリン代等実費」または任意の謝礼を受け取ることは問題ない。
- ただし、運転役務の報酬の名目で、実際には利用者から運転役務提供者に運送の対価を支払っているとみられる場合(単に車両提供者を介して運送の対価を収受しているとみられる場合)は、有償運送が行われているとみなされ、許可や登録を要します。
- 運送サービスの仲介者が仲介手数料の受領および、運送サービスの提供者に対する謝礼および実費の代行受領する場合
- 運送サービスの提供者および、当該サービスの利用者から仲介者に対して報酬を支払うのは問題ない。ただし、仲介の態様によっては旅行業等とみなされる場合があり、関係法令に留意が必要です。
- 運送サービスの仲介者が利用者から任意の謝礼およびガソリン代等実費を代行受領し、運送サービスの提供者に支払うことは問題ない。ただし、運送サービスの提供者が名目や支払方法のいかんを問わず、仲介者もしくは仲介者以外の第三者を通じて謝礼および実費を超える金銭などを収受することにより、運送の対価を収受したとみられる場合は、有償運送が行われているとみなされ、許可や登録を要します。また、仲介者が運送サービス提供者に対して、仲介手数料からキックバックするなど、任意の謝礼およびガソリン代等実費を超える金額が運送の対価とみられる場合も、有償運送が行われているとみなされ、許可や登録を要します。いずれにしても、仲介サービスを隠れ蓑にして有償運送することは認められません。
- NPO法人等が同法人の職員に対して報酬を支払う場合
- NPO法人等が、同法人の管理下にある運転手(職員・登録ボランティア等)に対して、NPO法人等からの指示に応じて第三者を無償で運送し、当該業務の遂行にかかる報酬を支払ったとしても、それは「運送サービス提供に対する反対給付」とはならない。
- 職員や登録ボランティアがNPO法人等の指示に基づき、マイカーを用いて無償運送を行った場合も同様。運送主体のNPO法人等が利用者から任意の謝礼およびガソリン代等実費を収受することはもちろん、ボランティア輸送に協力してもらった謝礼・報酬等(運送主体と利用者間で収受されるものではない)について、NPO法人等から運転者に与えることは問題ありません。
許可又は登録を要しない運送(無償運送)の留意点
これら「許可又は登録を要しない運送(無償運送)」のサービスは、運転する者が運転免許証を持っていれば、送迎車を運転することが可能とは考えられますが、留意事項としては以下について利用者が十分認識した上でサービス提供が行われる必要があります。
- 上記の運送行為は道路運送車両法上の法規制の対象外であり、同法が定める輸送の安全および利用者保護のための措置が担保されていない旨(自主的に措置を行っている場合にはその旨)
- 無償運送の場合、自動車保険(任意保険)の加入義務がないため、任意加入になること
- 事故が生じた場合の責任の所在
- 損害保険(自動車保険(任意保険)および損害賠償責任保険など)の加入の有無および補償内容
また、無償運送では有償運送とは異なり、チャイルドシート(幼児用補助装置)の着用免除規定が適用になりません。自動車の構造上、チャイルドシート(幼児用補助装置)を固定して用いることができない座席など以外の場合は、原則としてチャイルドシート(幼児用補助装置)を装着しなければならない点にも留意が必要です。
そのため、無償運送を行う上でチャイルドシート(幼児用補助装置)の用意が難しい場合は、乗車可能な対象者(年齢)を6歳以上に限定する必要があります。
根拠(幼児用補助装置):道路交通法施行令第26条3の2第3項第3号
上記の無償運送(道路運送法の許可又は登録不要の運送)について、不明点がある場合は運輸局および運輸支局に問い合わせしてください。
その他、こういったケースがどのような運送形態(有償運送・無償運送)に当てはまるのか、といった個別事案についても上記と同様です。
法規制の対象となるかどうかの確認のために当社にご質問いただいても、このようなご質問にはお答えが出来ません(お役に立てることはありません)のでご容赦ください。仮に、何らかの回答を当社から行ったとしても、それは何らかの保証には繋がらないからです。
許可又は登録を要しない運送のメリット・デメリット
許可又は登録不要の運送についての、メリット・デメリットについて、一般的にタクシーや有償運送と比較して、
- 事業所に入る収入として、運送中は反対給付(人件費)を除く車両にかかる実費までなので、単独では営利事業として成立しないが、複合的なサービスや差別化要素(付加価値)として実施するのはあり
- 既にタクシーや有償運送を行っている事業者でも、一部に許可又は登録不要の運送を取り入れても良いのではないか
- 介護・障がい福祉事業以外の事業にも取り入れることができる
- 運送する法人の種類(営利・非営利等)や、法人・団体・個人といった縛りがない
- 利用者層の制限がない(利用者が健常者でも、介助が必要な高齢者・障がい者でも送迎可)
- 単独乗車・複数乗車といった部分や、使用車両の大きさや種類の制限がない
- 行政による管理・監督がないので自由な一方で、適正な自主管理が必要
- 当たり前ですが車両の日常点検や点呼(アルコールチェックを含む)、安全運転管理などの業務は必須
- 2種免許の取得や、運転者講習の受講といった事前準備が不要
ただし、有償運送と比較し、まったく研修未実施といったことでは不安な場合に備え、当社では送迎ドライバー研修を行っています。定期的な研修実施も可能です。よろしければご検討ください。
訪問介護・居宅介護等の事業所が、通院等乗降介助などの介護報酬の請求を行う場合、反対給付を請求しない場合は運送の許可や登録が不要!
訪問介護・居宅介護等の事業所に所属している運転者が、自らの自動車を用いて送迎輸送を行うことに伴い、通院等乗降介助・身体介護中心型等の介護報酬(介護給付費)の請求を行う場合には、運送中に反対給付(運転手の運転中の人件費を含むもの)や介護報酬が発生しなければ有償運送とはならず、利用者を送迎する場合に道路運送法上の許可や登録は不要となりました。
乗車中も介護報酬や反対給付(運転手の運転中の人件費を含むもの)を利用者に請求する場合には、本ホームページで案内している道路運送法上の許可や登録を受けると、介護保険や障害者の個別給付などを算定しながら、送迎を行うことができるようになります。
- 福祉有償運送(79条登録)
- もしくは、交通空白地有償運送(79条登録)
- 訪問介護員等による有償運送(78条許可)
- もしくは、介護タクシー(福祉輸送事業限定・4条許可)や特定旅客自動車運送(43条許可)
有償運送を行う場合、上記のいずれかの許可または登録を要することとなります。
介護保険の訪問介護や、障害者総合支援法に基づく各種サービス
有償送迎にかかわる、介護保険上の訪問介護(要介護者対象)や、市町村事業の介護予防・日常生活支援総合事業(要支援者や基本チェックリスト該当者が対象)、障害者総合支援法に基づく居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・移動支援との関係について、以下の記事でまとめました。
福祉有償運送・訪問介護員等による有償運送を始めるには、それぞれハードルがある
福祉有償運送や、訪問介護員等による有償運送を始めるには、それぞれ一定のハードルがあります。詳しく紹介します。
福祉有償運送のハードル(交通空白地有償運送も同様)
市町村または都道府県等が主宰する、地域公共交通会議等(地域公共交通会議、協議会、運営協議会)を開催し、これらの場においてタクシー等の公共交通機関によって移動制約者に対する十分な輸送サービスが確保されていないと認められ、その必要性について十分な協議が調う必要があります。
地域公共交通会議等で協議が調った後に、運輸支局等で実施団体の登録を行います。
上記の条件は、福祉有償運送はもちろん、交通空白地有償運送も同様です。
福祉有償運送・交通空白地有償運送では、白ナンバー車での保険外サービスでの(自費による)送迎輸送が可能
福祉有償運送や、交通空白地有償運送では、自家用自動車(白ナンバーもしくは黄色ナンバー車)を用いて、保険外サービスとしての(いわゆる、利用者の支払いが自費による)送迎輸送を行うことが可能です。
白ナンバー車で保険外サービスでの(自費による)さまざまな目的地への送迎輸送が行える、唯一の選択肢といっても過言ではありません。
当社ブログに、福祉有償運送・交通空白地有償運送の登録の流れなどの解説記事がございます。
訪問介護員等による有償運送のハードル
訪問介護もしくは居宅介護等の事業所指定だけではなく、事前に必ず介護タクシー(福祉輸送事業限定・4条許可)または特定旅客自動車運送(43条許可)の許可の取得が必要になります。
これらの自動車は、緑ナンバーもしくは黒ナンバー車となります。運転手も、2種免許所持者が必要となります。
介護タクシーまたは特定旅客自動車運送の許可を取得した後に、訪問介護員等による有償運送の許可申請を行います。
訪問介護員等による有償運送では、保険外サービスの提供(送迎輸送)が行えない
保険外サービスとしての(いわゆる、利用者の支払いが自費による)送迎輸送を行う場合には、介護タクシー(福祉輸送事業限定・4条許可)を用いて行います。つまり、2種免許の運転手が、緑ナンバーもしくは黒ナンバーの自動車を用いて送迎輸送を行います。
自家用自動車を用いた訪問介護員等による有償運送では、ケアプランの範囲内や介護報酬の発生する範囲内での送迎輸送(つまり、通院等乗降介助や身体介護中心型などの介護報酬(介護給付費)が伴う送迎)に限定されます。
通院等乗降介助・身体介護中心型等の送迎輸送は、介護タクシーでも行うことができる
通院等乗降介助・身体介護中心型等の介護報酬(介護給付費)が伴う送迎輸送は、自家用自動車だけが行うことができるものではありません。事業用自動車(緑ナンバーもしくは黒ナンバー車)である、介護タクシー(福祉輸送事業限定・4条許可)でも行うことが可能です。
これは、一般的に「介護保険タクシー」と言われるものです。
まとめると、介護タクシー(福祉輸送事業限定・4条許可)の許可を取得している訪問介護・居宅介護等の事業者は、介護タクシーでのみ自費による送迎を行うことができ、介護報酬(介護給付費)を伴う送迎は、介護タクシーおよび訪問介護員等による有償運送で行うことが可能です。
ただし、介護タクシー・訪問介護員等による有償運送ともに、それぞれ許可を取得する必要があります。
当社ブログに、介護タクシー・訪問介護員等による有償運送の許可取得の流れなどの解説記事がございます。
通院等乗降介助(介護保険タクシーやぶら下がり許可)や、移動支援などについては、以下の記事にまとめました。
自家用自動車による有償運送にかかわるQ&A
自家用自動車による有償運送について、様々な疑問について回答いたします。
- 自家用自動車を用いて有償運送を行うには、どの資格が必要ですか?
-
- 福祉有償運送(79条登録)
- 交通空白地有償運送(79条登録)
- 訪問介護員等による有償運送(78条許可)
を実施するためには、福祉有償運送運転者講習の修了等が必要になります。運転者が取得すべき資格等の詳細は、こちらの記事をご確認ください。
通学通園に係る有償運送の場合においては、資格取得(講習修了)は不要です。
- セダン等運転者講習が必要な場合は?
-
福祉有償運送で、福祉車両以外の自動車を用いて送迎輸送を行う場合のみ必要になります。運転者が取得すべき資格等の詳細は、こちらの記事をご確認ください。
ケア輸送サービス従事者研修修了者、介護福祉士、訪問介護員、居宅介護従事者の場合には、セダン等運転者講習の受講が免除となります。
- 運転手は全員、資格が必要ですか?
-
運転手全員、福祉有償運送運転者講習の修了等が必要になります。運転者が取得すべき資格等の詳細は、こちらの記事をご確認ください。
- 無許可で(許可や登録を行わずに)有償運送を行うとどうなる?
-
無許可で運送中の反対給付(運転手の人件費を含むもの)を請求する有償運送を行うと、刑事責任を負う場合があります。その具体的な事例は以下の通りです。
無許可で有料スクールバス運行、学校法人など書類送検/横浜
無許可で有料のスクールバスを運行したとして、鶴見署は8日、道路運送法違反(有償運送)の疑いで、学校法人「ホライゾン学園」と、担当理事の男(67)を書類送検した。
カナロコ(神奈川新聞)の記事より引用(2010年7月9日の記事)有償運送の許可や登録の流れなどについて、以下の記事で解説しています。
- 送迎代として請求せずに、あくまで買い物付き添い代として請求した場合はどうなる?
-
運送中において反対給付(運転手の人件費を含むもの)を請求する場合には白タク行為に該当します。
他にも、「買い物付き添い代」としての名目ではなく、運送中も「写真撮影代」としてトゥクトゥクで送迎を行った場合に、白タク容疑がかけられている事案もあります。
男は県警の調べに「運賃ではなく写真撮影代」などと説明したが、15分3千円などの料金をとり、客を乗車させてホテルや駅に移動していることなどから、白タク行為にあたると判断した。
朝日新聞デジタルより引用 - どこまでが白タク行為(有償運送)に該当しない?
-
具体的には、ガソリン代・有料道路代・駐車料金・保険料の合計金額(実費徴収)までは、白タク行為(有償運送)に該当しないとされています。
また、自己の施設の利用を目的とする送迎を行う場合、送迎の有無によって対価・報酬に差が発生しない場合や上記の実費徴収を行う場合には、自家輸送(無償運送)となり、許可や登録は不要です。
通所・施設介護系の送迎の場合には、以下の送迎加算や減算がありますが、
デイサービス(介護) 利用者に対して、居宅と事業所間の送迎を行わない場合、送迎減算(片道につき-47単位) 日中・短期サービス等(障害) 送迎加算(Ⅰ)21単位もしくは、送迎加算(Ⅱ)10単位など これについては、2024年3月29日に厚生労働省のから出された「介護輸送に係る法的取扱いについて、介護予防・日常生活支援総合事業による高齢者の移動支援に係る交通施策との関係等について」の事務連絡によると、道路運送法上の許可や登録は不要と明記されています。
- 今行っている送迎が有償運送に該当するかどうか不安です。
-
お近くの運輸支局にお尋ねください。
福祉有償運送運転者講習・セダン等運転者講習の受講が必要な方は、以下のページからお申込みください。ご希望日がない場合には、出張講習にも対応しています。
自家用自動車による有償運送には、貨物輸送タイプもある
自家用自動車による有償運送は、人の送迎輸送を行うだけではなく、貨物輸送の分野でも活躍しています。たとえば、以下のものがあります。
- 事故車等の排除業務に係る有償運送許可(自家用車積載車による有償運送許可)
- 繁忙期有償運送(貨物自動車運送事業者による、繁忙期等の有償運送許可)
- 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの輸送における有償運送
- 新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえたタクシー事業者による有償貨物運送
自家用自動車による有償運送は限定的な用途で、対応範囲が幅広いのは介護タクシー
自家用自動車による有償運送には、実施可能な法人が限られたり、細かい部分で輸送条件が限られたりと、様々な制限があります。送迎の対象者を高齢者や障害者に限れば、もっとも制限がないのは事業用自動車(緑ナンバーもしくは黒ナンバー車)の介護タクシー(福祉輸送事業限定・4条許可)です。2種免許をお持ちの方であれば、介護タクシーが現実的な選択肢となります。
健常者を含む送迎輸送を行う場合には、自家用車活用事業や交通空白地有償運送
まったく病気をしていない健常者を含む送迎を行う場合には、自家用自動車を用いたものは自家用車活用事業(法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送)や交通空白地有償運送となりますが、実施可能なエリア(地域)は限られます。具体的には、バスやタクシーなどの公共交通機関で住民などに対する移動手段が確保できないと認められる地域や時間帯に限られます。
交通空白地有償運送では、住民などに対する日常的な移動手段としてはもちろんですが、観光利用を目的とした送迎輸送に活用することも可能です。ただし、交通空白地有償運送の場合、観光利用を目的とした送迎輸送を行う場合には、その利用目的を含めて地域公共交通会議等で協議が調っていることが条件のようです。
もっとも制限がないのは、緑ナンバーのバスやタクシーの開業
その制限をなくすためには、事業用自動車(緑ナンバー)のタクシーやバスの開業が選択肢となりますが、そのハードルは相当高くなります。
自家用自動車による有償運送の登録・許可の要件や手順について調べる方法
自家用自動車による有償運送(送迎輸送を行うもの)の登録・許可の要件や手順などについて、詳細な記事は当社のブログで解説しています。
それぞれ、上記リンクよりお読みください。
【最後に】この記事を読んでいただいたみなさまへ
この記事を読んでいただいて、みなさまの現場でお役立ていただければ大変うれしく思います。
また、記事をお読みいただいた方から、時折当社へ「福祉有償運送」や「訪問介護員等による有償運送(ぶら下がり許可)」などの許認可申請に関するご質問やご要望をいただくことがございます。しかしながら、ある程度以上のお話しになった場合には、該当する許認可申請などについては、必ず管轄の行政機関へ直接お問い合わせいただくようにご案内させていただくか、もしくは行政書士へお繋ぎをするなどの対応させていただく場合がございますのでご了承ください。
 スタッフより
スタッフより当社では行政書士が不在のため、一定の内容以上の許認可申請にかかわるお話しになった場合については、上記の通り回答できない場合がございますので予めご容赦いただくますようお願い申し上げます。